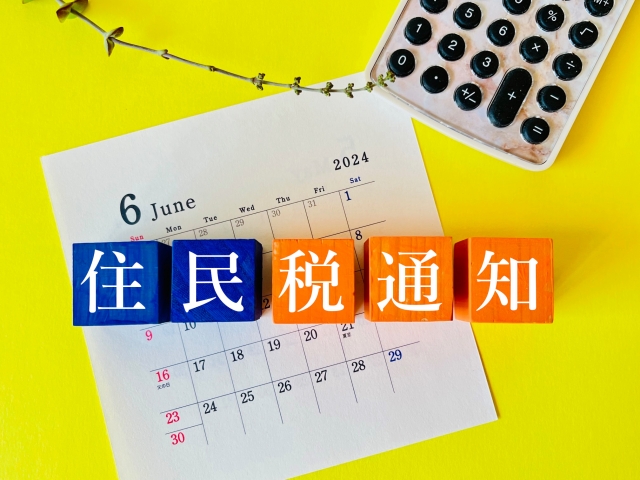【個人事業主】個人住民税の納付・納付方法と資金繰りの考え方
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
個人住民税の納付にまつわる
納付方法と資金繰りを解説します。
それでは、スタートです!!
個人住民税とは?納付はどうしたらよいか?
個人住民税とは
所得税の確定申告を基に市区町村で計算され、個人に対して課税される税金
になります。
個人住民税は前年分の確定申告
を基に計算されて翌年に決定通知書
と一緒に4枚の納付書が送られてきます。
おおむね、5月~6月中旬までには
郵送されてくるはずです。
令和6年分は続々郵送されて
来ていると思います。
さて、納付は4回と申し上げたように
4回払いになっています。
4回とも異なる納付期限(支払期限)
があります。
結果、納付期限までにそれぞれ
納付すれば問題はありません。
市区町村によって異なる
場合があると思いますが
おおむね次のようになります。
1回目:6月30日
2回目:8月31日
3回目:10月30日
4回目:翌年1月31日
ただし、納付期限が土日
祝日になっていることがあります。
この場合には、翌日以降にくる
最初の平日まで納付期限が後ろに
なります。
令和6年分の1回目の納付期限は
7月1日が納付期限になっていると
思います。
6月30日が日曜日だから
翌日以降の平日である7月1日
の月曜日になっているわけですね。
些細なことではありますが
4回分を一気に納付したいという
要望もあると思います。
これを実現するためには以下の
2つの方法があります。
①4枚の納付書を使ってすぐに全額支払ってしまう方法
②市区町村の課税課に電話して一括納付の納付書を送ってもらい支払う方法
市区町村に連絡することが
面倒であれば郵送されてきた
4枚の納付書を使って納付しても
何ら問題はありません。
個人住民税の納付方法
個人住民税の納付方法には
いくつか方法があります。
・口座振替
・ペイジー
・コンビニ納付
・アプリの請求書払い
・クレジットカード納付
・窓口で現金支払い(銀行や市区町村でできます。)
口座振替は決定通知書と同封
されている口座振替依頼書を
市区町村に送る人手間があります。
口座振替が完了すると4回ごとの
納付期限に登録した口座から
住民税が引落されます。
ポイントは引落される日に
納付金額以上の金額が口座に
ないと口座振替できません。
事前に口座残高を確認しておく
とよいかと思います。
ペイジーとは税金などの支払いに
手数料がかからずに振り込むことが
できる仕組みです。
銀行だとATMやインタネットバンキング
でペイジーが使えることが多いです。
一部ネット銀行ではペイジーが
使えないことがあるので機能を
確認しておくとよいです。
ペイジーでは納付書に書かれている
収納機関番号などの数字を入力して
納付することになります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
コンビニ納付では納付書に
印刷されているバーコードを
読み取って納付します。
現実では納付金額の現金を
コンビニ持っていく必要があるので
現金も忘れないようにしたいです。
スマホの○○Payアプリでの
請求書払いを使って納付できます。
具体的には○○Payアプリの
請求書払いを起動して納付書の
バーコードを読み取って支払う
ことになります。
ただし、○○Payに資金移動
できる金額には制限があります。
納付できないこともあるため
資金移動の上限を確認しておくと
使うかどうかの判断ができます。
最後にクレジットカード納付です。
スマホのモバイルレジアプリを
入れることでできます。
こちらも○○Payと同様に
モバイルレジで納付書の
バーコードを読み取って
クレジットカードで支払うこと
ができるようになります。
但し、5千円ごとに決済手数料が
かかることになります。
しかし、クレジットカードのポイント
対象にもなりますので
決済手数料以上のポイントが
手に入る場合には損はしない
支払方法だと思います。
個人住民税の資金繰りの考え方
個人住民税の納付書が知らずに
いきなり来ると焦ると思います。
住民税の恐ろしさは前年分を
課税対象に計算されて当年に
納付を求められます。
令和6年分の個人住民税では
令和5年分の確定申告を基に
計算されています。
おおむね、どうやって住民税を
支払ったよいのか?と考えることに
なるのと思います。
まずは、4回に分かれていますので
それぞれの納付期限までに納付
できるお金を用意するのが先決です。
お金に余裕があれば一括納付も
考えられますが
一般的にはそんな余裕はないので
4回にわたって納付します。
ここからは資金繰りの考え方
を解説します。
1回目の納付期限は令和6年分では
7月1日になっており日が浅いので
どうにかお金をやりくりして
納付金額をねん出することになります。
これでもどうにかならない場合は
納付期限後1か月以内に納付すれば
督促されませんので
何とか8月中に納付を目指します。
ただ、8月末には2回目の納付期限が
くるため2回目の金額の用意も必要
になります。
遅れれば遅れるほどどんどん
資金繰りが悪化する可能性が
あります。
2つの選択があります。
①生活費を切り詰めて納税資金を確保する
②商工会議所のマル経融資でお金を借りる
どちらかやりやすい方で
よいと思います。
マル経融資は低利の融資
なので返済する必要はありますが
一気に預金残高が増えるため
使い勝手がよい融資制度です。
編集後記
私は独立したのが5月だったので
いきなり前年分の住民税と
健康保険が重くのしかかった
のを覚えています。
結構大変でしたね。
今思うとマル経融資を受けて
しまえばよかったと考えています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務