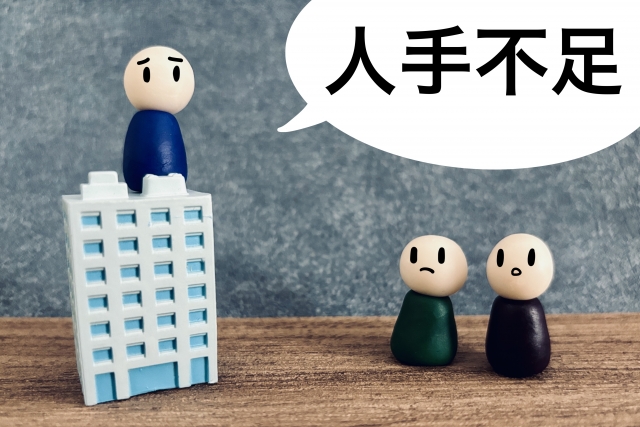【人手不足と出生数】中小企業は人手不足へどう対応したらよいのか?
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
中小企業の人手不足への対応を
考えてみました。
それでは、スタートです!!
令和5年の出生数から考える将来の生産年齢人口減少
厚生労働省が公表している
令和5年人口動態統計で
出生率は72万7288人で令和4年と比べて4万3471人減少
となっています。
令和6年以降も出生数が減る
トレンドがあると考えられています。
出生とは反対の死亡数を確認
してみると
157万6016人が死亡しており
令和4年よりも6966人増加して
過去最多になっています。
出生数から死亡数を引いた
自然増減数も減少になっており
令和5年では-84万8728人で
令和4年の-79万8291人よりも
5万437人減少して過去最大の減少です。
話は変わって生産年齢人口
という概念があります。
生産年齢人口とは15歳以上65歳未満
の人口を指し、イメージとしては
現役で働くことができて
主に経済活動を行う年齢層
という位置づけです。
要するに、お金を稼ぎ消費も
行う人口の層です。
当然ながら出生数が減っている
状況がありますので
生産年齢人口に加わる人は
今後減っていき
生産年齢人口から抜ける人の
方が増えていきます。
以上のことから生産年齢人口
の減少によって
今の経済を維持しようとするなら
より人手不足になります。
20年後の人手不足について理解する
さて、人が生まれて生産年齢人口
に達するまでには最低15年はかかります。
現状だと大学全入学時代に
突入していると考えられるため
大学に行くことが前提と
考えると
人が働くことになるためには
約20年くらい先になります。
事業者としては現在の人手不足
への対応を考えつつ
20年後の人手不足に対する
備えもしておく必要があります。
20年後の生産年齢人口推計では
約5580万人になり
総人口は約1億人になる
試算になっています。
言い換えると20年後には
人口の約半分強が働くことが
できる現役世代になります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
ここから考えられることは
若年層の獲得競争だけではなくて
各年代ごとの人の獲得競争に
中小企業は飲み込まれる可能性が
あると考えれます。
言い換えると、給与を高くした
としても人が雇えなくなる可能性
が出てきます。
今年できる人手不足対策を洗い出す
現状で20年後への備えをする
というのも夢物語のように感じる
と思います。
まずは今年できる人手不足対策
を考えてみることが肝心です。
基本的に人がかかわらないと
絶対できない仕事は人に任せる
というのが基本指針です。
この点、不要な人手は最初から
手放すことになります。
言い換えると、なんでも自社でやる
時代は少しずつ変化しており
外注に頼るものは外注にして
自社で行うことは自社にする
ことです。
専門的なものであればあるほど
外部に任せるという考えです。
そのうえで、自社の事業だけに
集中するようにシフトすると
よいかと思います。
こうした考え方によって
自社がしなければならないこと
外注することで解決できることを
洗い出して人手不足対策をする
ことになると考えています。
編集後記
人手不足対策というとすぐにIT
を連想するかもしれません。
確かにITを使うことで一定程度
人手不足対応は可能だと思います。
しかし、本質的には自社でやる
必要がないものを内製化して
その必要がない業務のために
人を雇い仕事をしてもらっている
ことがあります。
私の考えは自分でやる必要がない
ものについては外部の専門家に
頼った方が人を雇うよりもコストが減り
追加で人を雇う、育成する
仕事をしてもらうといったリソースを
自社の事業に向けた方が建設的では
ないかということです。
外注することにより減ったコストは
自社の事業に必要な従業員の給与で
還元したりもできます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務