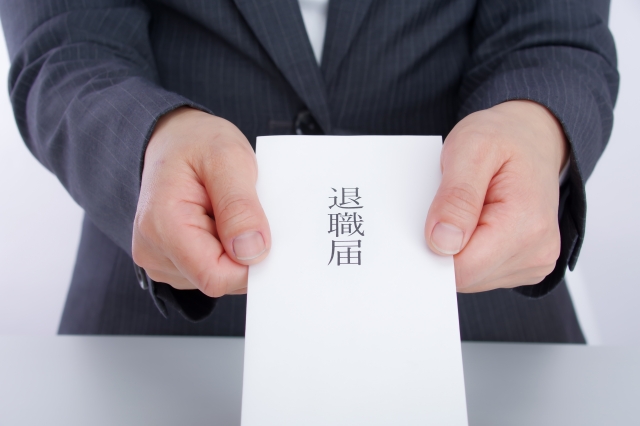【退職金の税金】退職金があった場合を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
退職金を得た場合を解説します。
前提として一般の従業員が
退職金をもらったこととします。
それでは、スタートです!!
退職所得の受給に関する申告書を提出して手取減少を抑える
退職金をもらった場合には
何もしなければ
退職金に税率をかけた金額が
源泉徴収されて支給されます。
税率は所得税が20.42%になり
住民税は10%です。
何もしないと30.42%の税金が
退職金から引かれて支給される
ことになります。
手取の減少を抑える方法があり
退職所得控除があります。
こちらは
退職所得の受給に関する申告書
を会社に提出することで
退職所得控除が適用できます。
具体的には
(退職金-退職所得控除)×1/2×税率
という計算になります。
結果、退職所得の受給に関する
申告書を提出することで
手取が減ることを抑制する
ことができます。
退職所得控除の活用と退職金の計算方法
退職所得控除は次のように
計算されます。
①勤続年数20年以下
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)②勤続年数20年超
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数は1年未満の期間は
切り上げて1年になります。
退職所得控除の最低額は80万円
になっており
20年を超えると超えた部分の
控除額も増える仕組みになります。
非常に大きな金額が控除額
になる仕組みなので
活用したいところです。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
では実際に具体例を出して
計算をしてみたいと思います。
具体例
・退職金:500万円
・勤続年数10年3か月
退職所得の受給に関する申告書を提出している
とします。
退職所得控除の計算
勤続年数が10年3か月なので、勤続年数は11年になり
40万円×11=440万円になります。
退職金の源泉徴収(所得税)
(500万円-440万円)×1/2×5%=15,000円
税率は退職所得の源泉徴収税額表の速算表から適用します。
退職金の源泉徴収(住民税)
(500万円-440万円)×1/2×10%=30,000円
退職金の手取り額
500万円-1.5万円-3万円=4,955,000円
になります。
退職金の確定申告について
退職金が支給された年では
確定申告をしなければならないのか
というと
必ずしも確定申告はしなくても
よいことになっています。
なぜなら、退職金は他の収入
とは分離して計算するため
支給時に源泉徴収されていれば
課税関係は終了するからです。
しかし、次の場合には
確定申告で反映することになります。
①医療費控除などで確定申告する場合
②退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合
医療費控除、ふるさと納税
住宅ローン控除の1年目などで
確定申告をすることになる
場合には確定申告にて
退職金も含めた確定申告書を
提出することになります。
退職所得の受給に関する申告書を
提出していない場合には
退職金を支給されたときに
源泉徴収が多く行わていますので
確定申告にて退職所得控除を
適用して所得税を取り戻す
ことが可能です。
他の収入との兼ね合いもあるので
必ず還付になるとは断言できませんが
一般的には還付申告になる
可能性が高いです。
編集後記
退職金で源泉徴収された
税金は会社でどのように処理
されるのかというと
会社は源泉徴収した所得税
と住民税を納付します。
退職金の所得税は毎月の
給与から天引きされる所得税
と同じ納付書を使います。
住民税は、退職金を支給する
従業員の市区町村の納付書に
書いて納付します。
会社が意地悪で源泉徴収している
というのではなくて
源泉徴収することが義務なので
天引きした税金は適正に納付する
ことになります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務