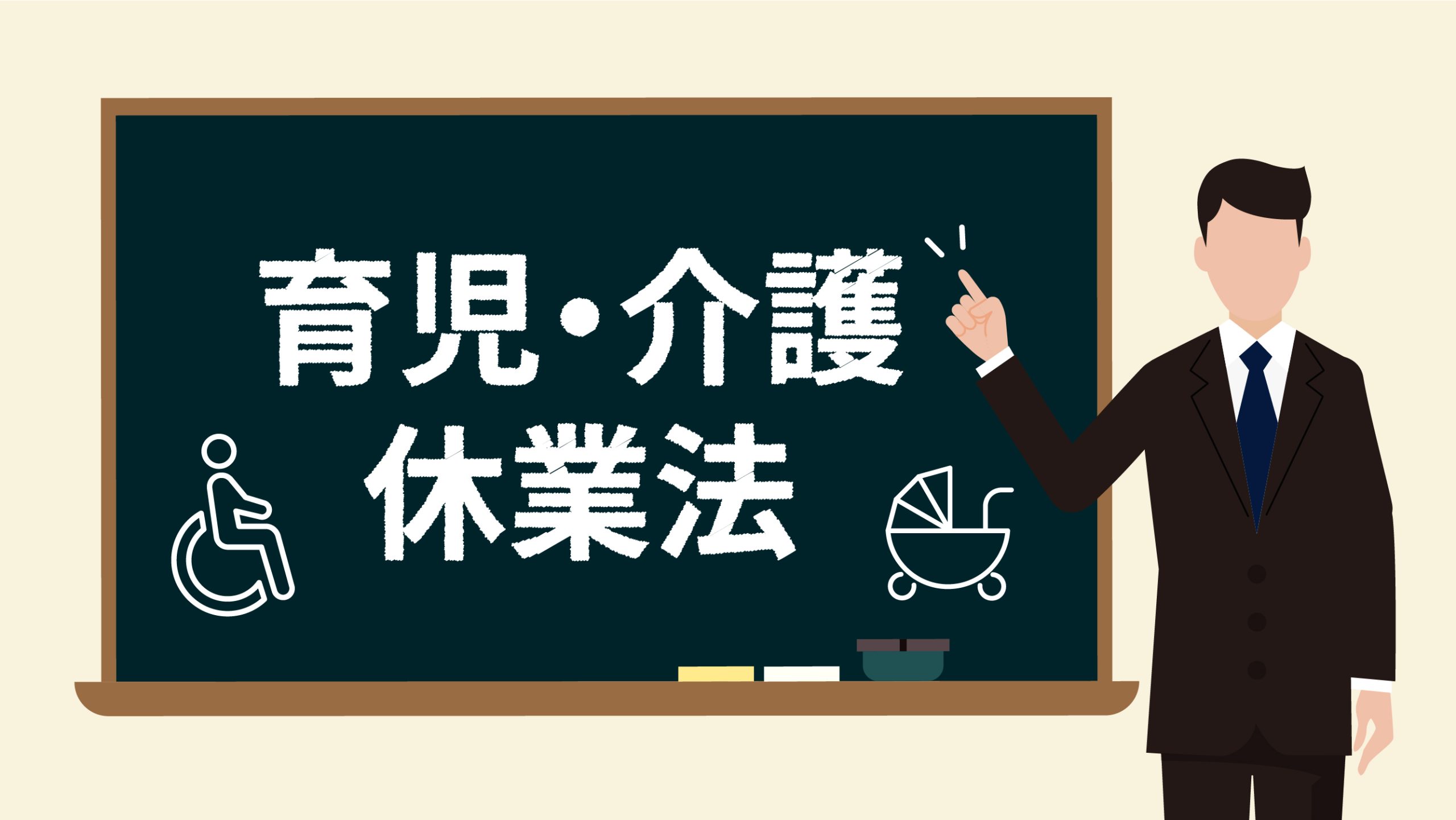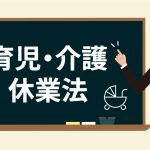【育児介護休業法】会社や従業員向けの支援制度、会社がやってはいけないことを社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
育児介護休業法の改正による
会社や従業員への支援制度や
会社が従業員に対してしては
ならないことを解説します。
それでは、スタートです!!
会社が育児介護休業法へ対応するための支援制度
育児介護休業法の改正に伴い
会社は改正に対応する義務の
範囲が広がりました。
中小企業では少し厳しい内容に
なっていることがあるため
厚生労働省は2つの支援制度を
設けています。
中小企業育児・介護休業等
支援事業とは
制度整備、育休取得・復帰する社員のサポート、育児休業中の代替要員の確保・業務代替等について社労士等の労務管理の専門家が無料でアドバイスしてくれる制度
になります。
中小企業で顧問社労士がいない場合
に利用することになる制度だと
考えます。
支援回数は最大4回までで
2回目以降はプラン策定の具体的な
相談などを引き受けることに
なっているようです。
令和6年度の申し込みは終了して
いるので
令和7年度の申し込みが
今後始まったときに
申込を行うことになります。
一定の要件を満たしたときに
両立支援等助成金の申請で
助成金の受給ができます。
現行制度のコースは
・出生時料率支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
・育休中等業務代替支援コース
・柔軟な働き方選択制度等支援コース
・不妊治療両立支援コース
になっています。
厚生労働省の該当サイトでは
それぞれのコース別のリーフレット
がおいてあります。
申請に使うための様式がエクセル
PDFでおいてあり
記載例もありますので
申請書等の作成ができます。
助成金は電子申請をすることに
なっておりGビズIDが必須です。
申請を行う前にGビズIDの取得を
行う必要があります。
従業員が育児休業をした場合の支援制度
育児休業給付金
があります。
こちらは雇用保険から従業員へ
支給される制度になっており
育休中では給料がなくなるため
その補填として支給されるものです。
令和7年4月以降は改正が入り
次の2つが創設されます。
・出生後休業支援給付金
・育児時短就業給付金
したがって、制度上では要件を
満たすことで以下の4つになります。
・出生時育児休業給付金
・育児休業給付金
・出生後休業支援給付金→令和7年4月から
・育児時短就業給付金→令和7年4月から
それぞれいつの対象になるのか
というと
出生時育児休業給付金
出産から8週間の期間
育児休業給付金
出産から子が1歳になるまで
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
出生後休業支援給付金
原則出産から8週間まで、産後休業をする場合は16週まで
育児時短就業給付金
出産から子が2歳に達するまで
出生後休業支援給付金と
育児時短就業給付金の
支給要件などについて確認します。
出生後休業支援給付金の要件と
支給額
①支給要件
・労働者が対象期間内に、子について出生時育児給付金が支給される産後パパ育休または育休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと・労働者の配偶者が、「この出生日または出産予定日のうち早い日」から「この出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること
②支給額
休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
出生後休業支援給付金の
要件と支給額
①支給要件
・2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者であること・育児休業給付の対象になる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間があること
・初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者である月
・1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
・初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
・高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
②支給額・支給率
原則、育児時短就業中に支払われた給料の10%を支給。ただし、育児時短就業開始時の給与水準を超えないように調整される
要するに新たに創設される
給付金のイメージは
出生後休業支援給付金が
出生時育児休業給付金の上乗せで
育児時短就業給付金は時短で
減った分の給料の補填をする
感じになります。
会社が従業員へしてはいけないこと
育児休業や介護休業をする
従業員に対して会社がやっては
いけないことをまとめます。
①改正前からの禁止事項
育児休業・介護休業を理由に、会社が従業員を解雇・退職強要、正社員からパートへの契約変更の強要などの不利益取り扱い②改正による不利益取り扱いをする理由の追加
・感染症に伴う学級閉鎖などで子の看護等休暇をしたこと
・家族の介護をする申出をしたこと
・妊娠出産の申出などで、従業員が仕事と育児の両立に関する意向表明をしたこと
・柔軟な働き方を実現するための措置の申出・利用をしたこと
以上の行動をきっかけにして不利益な取り扱いをしてはならないです。
不利益な取り扱いの典型例
として公表されているものでは
・小学1年生の子のクラスが新型コロナウイルス感染症で学級閉鎖となったので、子の看護等休暇を5日間取得し復帰しようとしたところ、さらに1週間自宅待機するよう命じられた。
・母親が脳梗塞で倒れ介護が必要な状態となったことを社長に伝えたら、介護はいつ終わるかわからないから退職願を出してから休むようにと言われ、会社所定の退職願にその場で署名するよう強要された。
厚生労働省 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説から引用
ハラスメントの典型例としては
・子の卒園式のために子の看護等休暇の取得について上司に相談したら「迷惑だ。自分なら取得しない。だからあなたもそうすべき。」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。
・父親が介護が必要な状態となったこと、介護休業を取得しようと思うと周囲に伝えたら、同僚から「今の忙しい時期に休むなんて自分なら時期を考える。」と言われた。「今休んで早めに介護施設を探したい。」と再度伝えたが、再度同様の発言をされ、苦痛に感じた。
厚生労働省 育児・介護休業法 令和6年(2024年)改正内容の解説から引用
禁止事項については一般的に
会社が行ってはいけない行動
というのはイメージがつくと
思います。
しかし、ハラスメントの印象は
ある言葉に相手がどのように反応
するかどうかによって
ハラスメントになるかどうかが
決まるといっても過言ではないです。
制度として令和7年4月以降から
義務になりますので
余計なことは言わずに
会社は手続きを行えばよいと
考えます。
編集後記
よくある典型例としては
産前産後休業から育休になり
育休期間中に2子の妊娠があり
産前産後休業から育休という
流れが発生する可能性があります。
こうなると復帰後のキャリアなど
復帰ができる制度が整っている
会社でないと少し厳しいかもしれません。
復帰制度がないことが従業員に
バレていると2回目の育休後すぐに
退職願いからの有給休暇の取得で
退職してしまうことが発生する
可能性がありますね。
育児・介護については休業と
代替要員の確保
そして休業後の復帰までの
トータルで会社の体制を整える
ことが要求されてくるハードな
段階まで来ていると考えます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務