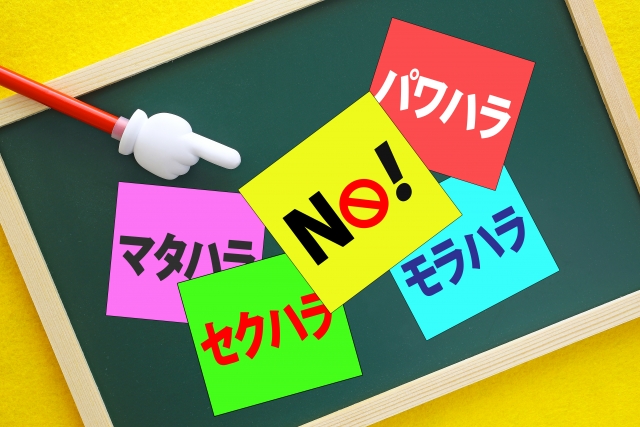【中小企業のハラスメント】ハラスメントの基本的な考え方と事業者の義務を社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
ハラスメントの基本的な考え方
を解説した記事です。
それでは、スタートです!!
ハラスメントの類型と事業者の義務
厚生労働省が認知している
ハラスメントの類型では
①パワーハラスメント
②妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメント
③セクシャルハラスメント
④カスタマーハラスメント
になります。
ハラスメントの類型は上記
4つになりますが
もっと大きなくくりでは
職場におけるハラスメント
としても厚生労働省は認知を
しているところです。
さて、法律では令和2年6月1日
施行でパワーハラスメント対策は
事業者の義務とされており
セクシャルハラスメント等の
防止対策も強化されている
ところです。
具体的には労働施策総合推進法
において根拠規定が整備されています。
内容は
パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法】
①事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備
②パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備
厚生労働省 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)の概要から抜粋
事業者が行う義務では
雇用管理として
パワーハラスメントに対する
相談体制の整備等があります。
もし事業者がきちんと対応
しないと労働局で対応しますよ
ということになります。
もし、国からの是正勧告を受けて
も事業者が従わなかったときには
企業名が公表される可能性
があります。
セクシャルハラスメントでは
セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法】
①セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
②労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止
厚生労働省 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)の概要から抜粋
見受けられるのが相談しても
臭い物に蓋をするといった対応
をする可能性があります。
つまり、セクシャルハラスメントを
訴えてきた従業員を左遷又は
畑違いの業務へ移動させて
なかったことにするなどです。
これはダメですよ!!
ということになっています。
ハラスメントへの対応とは?
事業者がハラスメント対策を
する前にどういったことが
ハラスメントになるのかを
知っておくことはポイントです。
まずはパワーハラスメント
を確認します。
厚生労働省が考えている
パワーハラスメントは以下の
3つがそろったものです。
①優越的な関係を背景として言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
③就業環境が害される
以下、具体例を確認します。
優越的な関係を背景として言動
業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。
例示
・職務上の地位が上位の者による言動
・同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
厚生労働省 職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!から抜粋
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。
例示
・業務上明らかに必要性のない言動
・業務の目的を大きく逸脱した言動
・業務を遂行するための手段として不適当な言動
・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
総合的な判断をすることになります。
厚生労働省 職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!から抜粋
就業環境が害される
当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。
この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を基準とすることが適当です。
なお、言動の頻度や継続性は考慮されますが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場合には、1回でも就業環境を害する場合があり得ます。
厚生労働省 職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!から抜粋
現場で注意するのは
優越的な関係を背景とする言動と
職場環境が害されることだと
考えます。
人間なのでこれらは
どこかでやってしまう可能性が
あると思います。
因みに、業務上必要かつ
相当な範囲を超えた言動は
意図的でないとできません
のでおおむね判断はしやすい
と考えます。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
次にセクシャルハラスメント
を確認します。
セクシャルハラスメントの
定義は次のようなことです。
職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。
厚生労働省 職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!から抜粋
分けると性的な言動により
労働条件について不利益を受ける
就業環境が害される
の2つに帰結することがポイントです。
前者は、セクシャルハラスメント
を受けたと報告した労働者を
会社が不当に扱うイメージで
後者はセクシャルハラスメント
を受けた労働者の就業環境が
害されることになります。
性的な言動とは
性的な内容の発言および性的な行動を指します。
①性的な内容の発言
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すこと等②性的な行動
性的な関係を強要すること、必要なく身体へ接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為等男女とも行為者にも被害者にもなり得ますし、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。また、被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であれば、セクシュアルハラスメントに該当します。
厚生労働省 職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!から抜粋
いわゆる話のノリとして
聞いてしまうことがありますが
相手側が嫌がっているにも
かかわらず下ネタをいう
などどいったことでも
該当してしまう可能性があります。
話やその場のノリでは
もはや通用しなくなっています。
事業者のハラスメント対策は
ハラスメントの内容を周知させ
必要以上の言動や会話を慎む
ようにすることです。
基本的には仕事上での会話や
指揮命令で行われた言動は
ハラスメントにならない
可能性が高いです。
しかし、セクシャルハラスメント
については問答無用で性的な言動
をすることがダメです。
個人的なことは聞かないように
するといった周知も効果があります。
従業員はハラスメントをメモしているかも
一般的には従業員がハラスメント
を受けることになります。
さて、現在ではネットなどで
士業を筆頭に法的な証拠集め
を解説していることがあります。
基本的には裁判まで行く前に
お互いに和解で済ませるでしょうが
相手に何かを主張するときには
確たる証拠が必要です。
このときに最も重要なのは
被害者が欠かさずされたことを
メモなどに記録を残しておくこと
になります。
手帳、日記などなんでもよい
ことになります。
世の中ではハラスメント
に対して拒否できる人と
拒否ができない人の
2種類がいると考えられます。
メモなどの証拠物を残す
場合にはハラスメントを拒否
できない人が行う可能性が
高いと考えられます。
メモを残す人の属性を想像すると
がまんにがまんを重ねてあるとき
一気に不満が爆発するのだと思います。
結果、事業者に相談なくいきなり
労基に駆け込まれる可能性があります。
現場ではこうしたことについて
なるべく早く対応しておくと
トラブルを最小限にすることが
できると考えます。
和解であっても基本的には
個人同士の争いごとです。
弁護士を双方とも立てて
話し合いを行い
慰謝料で解決することに
なるまで行ってしまうと
ハラスメントをした従業員
とされた従業員の両方が
会社を去ってしまう可能性が
高くなると考えます。
こうしたことにならない
ためにも当事者の間に事業者が
入り解決したり未然に防ぐ
必要があると考えます。
編集後記
最近、建設業にも女性が多く入る
ことがあるようです。
事務仕事の女性もいますが
大工として就労する女性も
増えているようですね。
今までの建設業では男社会なので
多少の下ネタなどは許容されて
来たのでしょうが
もう、そんなことは言って
いられない時代になっています。
ハラスメントはダメ絶対!!
なのです。
今後は建設業であっても
職人にはハラスメント研修を
受けさせるなどの対策が
必要になってくると考えます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務