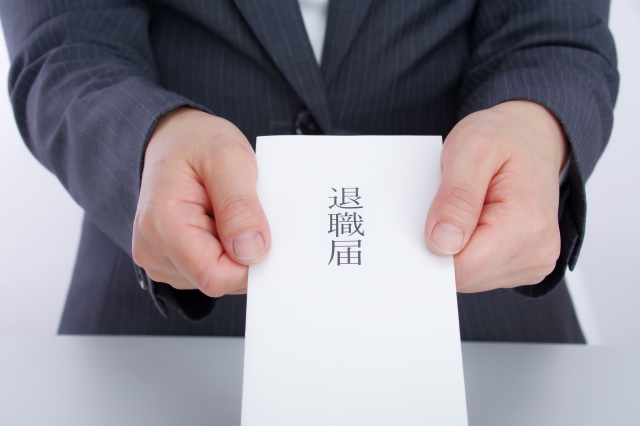【退職者の手続き】雇用保険・社会保険・税務関係手続きを税理士・社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
退職関係手続きについて
解説します。
それでは、スタートです!!
雇用保険の退職手続き
雇用保険の退職手続きとして
必ず必要なものは
資格喪失届
になります。
提出先
事業者の住所を管轄するハローワーク
提出期限
退職日の翌々日から10日以内
となります。
例えば、3月31日に退職だと
翌々日なので4月2日になり
ここから10日以内なので
4月2日から4月11日までに
資格喪失届を提出します。
従業員が離職票の交付を希望する
場合には以下の資料も添付します。
・離職証明書(3枚複写)
・支給期間の内訳と交通費がわかる賃金台帳又は給与明細
・出勤簿又はタイムカード(記載した期間すべて)
・離職理由の確認できる資料のコピー
離職証明書はハローワークで入手
可能になり3枚複写になっています。
離職証明書には給与や交通費を
書きますので書いた期間に対応する
出勤簿、賃金台帳又は給与明細が
必要になります。
出勤簿やタイムカードも同様の
期間になります。
離職理由の確認できる資料とは
・自己都合:退職願、労働者名簿など
・解雇:解雇通知書、労働者名簿など
・退職勧奨:退職願、労働者名簿
・定年:就業規則、再雇用に係る労使協定書など
・契約満了:契約書
といったものです。
社会保険の退職手続き
社会保険で必要な書類は
被保険者資格喪失届
になります。
雇用保険とは別の資格喪失届
になります。
提出先は
都道府県を管轄している日本年金機構の広域事務センター
又は
事業所の住所を管轄している年金事務所
になります。
提出期限は
事実発生から5日以内
とされています。
事実とは退職した日になる
ため退職日から5日以内に
手続きを完了させます。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
協会けんぽを前提にすると
添付資料が必要になります。
健康保険証又は資格確認書
になります。
退職者からは必ず健康保険証
又は資格確認書を返却して
もらう必要があります。
返却が難しい場合には
資格確認書回収不能届又は健康保険被保険者証回収不能届
も一緒に提出する決まり
になっています。
社会保険での資格喪失日の
考え方がポイントです。
退職による資格喪失では
退職日の翌日になります。
給与計算に与えるポイントでは
月末退職になると
資格喪失日が翌月の1日になるので
給与から天引きする社会保険の
サイクルによっては
2か月分の社会保険の天引き
が必要になることがあります。
税務関係の退職手続き
税務関係の退職手続きでは
所得税と住民税があります。
所得税では退職した月までの
月給、社会保険料等、源泉所得税
を反映した
源泉徴収票
を退職者へ交付します。
所得税の手続きは以上で
終了になり
特段、税務署へ何かの提出物が
発生することはありません。
退職金がある場合には
退職所得の受給に関する申告書
を書いてもらいます。
こうすることで退職所得控除
の適用ができます。
事業者に退職金規定がない場合は
退職金に関する合意書を作成し
退職者に認印などで印鑑を
押印してもらって退職金として
支給したことの証明書類にします。
住民税は
特別徴収にかかる給与所得者の異動届出書
を提出します。
こちらを提出することで
事業者は退職者から天引きする
特別徴収義務から解放されます。
本人には天引きされていない
住民税分の納付書が届く
という手続きになります。
退職日が1月から4月までの
場合には住民税を一括徴収する
ことが原則になります。
最後の給与支給で未徴収の税額を
超える金額になる場合には
一括徴収するというものです。
6月~12月までの退職では
本人の希望がある場合のみ
一括徴収することになります。
編集後記
事業者が退職手続きをする
場合には雇用保険、社会保険
税金関係と分けて
資料の収集とやるべきこと
作成する資料を分けて管理すると
効率的に進めることができます。
外国人従業員が退職して帰国する
場合には住民税では一括徴収する
協力があったりします。
外国人の場合には帰国されると
住民税の徴収が市区町村では
困難になる恐れがあるためです。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務