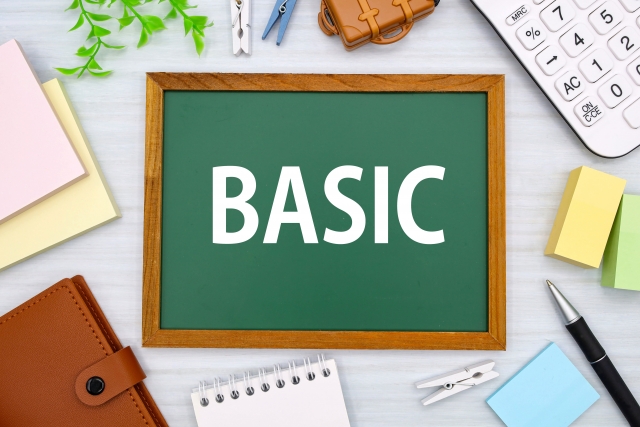【法人の社長向け】税務の基本知識を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
法人の社長向けの記事として
税務の基本知識を解説します。
それでは、スターとです!!
税務の基本知識(社長個人編)
- 所得税
役員報酬や給与など、個人の所得に対して課せられる税金です。- 住民税
役員報酬や給与など、個人の所得に対して課せられる税金で「所得割」と「均等割」があります。
法人の社長の立場として
会社から委任を受けて法人の
経営をすることになります。
経営をすることの対価として
法人は社長へ給与を支払います。
会社から社長へ支給される給与は
役員報酬と呼ばれます。
所得税は、役員報酬の支払いの都度
源泉所得税として概算の所得税が
天引きされます。
年末には、概算の所得税の精算として
年末調整を行って
年収に応じた正確な所得税を計算し
毎月天引きされてきた源泉所得税を
控除して精算を行います。
住民税は少しいびつな課税体系です。
住民税は給与が支払われた年の翌年
に課税される仕組みです。
令和6年度を基準にすると令和6年の
年収を基に令和7年分の住民税が
計算されます。
これが令和7年分として令和7年
6月以降に通知されてきます。
では、所得税と住民税の納付の
仕組みを確認します。
所得税は月給から天引きされた
源泉所得税になり納付します。
原則、天引きされた月の翌月
10日までに納付をします。
対して住民税は、普通徴収と特別徴収
の2つの納付形態があります。
普通徴収は社長個人へ納付書が
届いて個人で納付をする方法です。
特別徴収は源泉所得税と同じで
給料から1か月ごとに決まった
住民税を天引きして会社のお金で
天引きした月の翌月10日までに
納付をします。
実務上の留意点は普通徴収を
選択した場合には
普通徴収の住民税は会社の
お金で支払うことはできません。
理由は以下の通りです。
- 個人負担になっているものを法人のお金で支払うことができない
- 給料から天引きしていないため、法人のお金で支払うと社長の給与になってしまう
以上のことから会社のお金で
住民税を納付したい場合には
特別徴収を選択して住民税の
申告である給与支払報告書の
提出を行います。
税務の基本知識(法人編)
- 法人税
企業の利益に対して課せられる税金です。国税と地方税があります。- 消費税
商品やサービスの提供に対して課せられる税金です。企業は消費税を価格に上乗せして徴収し、国に納付します。- 固定資産税
企業が所有する不動産(土地や建物)に対して課せられる税金になり、減価償却資産では償却資産税という名前に変化します。
法人税は企業の利益に対して
課税されますが対象は
損益計算書の税引前当期純利益
になります。
損益計算書は会社の業績を計算する
仕組みの財務諸表になります。
消費税には計算方法が3つあります。
- 実額計算をする本則課税
- 収益の消費税に一定の控除割合を乗じて控除する簡易課税
- インボイス発行事業者が一定の要件で適用可能な2割特例
本則課税は
収益に対応する消費税(仮受消費税)-経費に対応する消費税(仮払消費税)
という計算を行います。
この場合に次のような申告に
なりえます。
- 納付申告
仮受消費税>仮払消費税の場合:納付になります- 還付申告
仮受消費税<仮払消費税の場合:還付になります。
一般的には本則課税でないと
還付申告になりません。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
簡易課税は
収益に対応する消費税-(収益に対応する消費税×みなし仕入率)
という計算になります。
みなし仕入率は行っている
事業ごとに決められており
90%~40%になっています。
つまり、上限の90%の控除だと
仮定すると収益に対応する消費税の
10%は納付することになります。
結果、ほぼ間違いなく納付になる
計算になります。
2割特例は
収益に対応する消費税-(収益に対応する消費税×80%)
という計算になっています。
上記の計算では収益に対応する消費税
の20%は納付になることから2割特例
と呼ばれています。
2割特例が適用できる事業者であれば
業種に関係なく80%の控除割合になります。
固定資産税は企業が不動産を持っている
場合に納付する税金になります。
対して償却資産税とは不動産以外の
動産などを150万円以上もっている
場合に納付する税金です。
償却資産税の対象になる資産は
パソコン、内部造作など幅広く
不動産と車両以外は償却資産税の
対象試算になる可能性が高いです。
税務の基本知識(社長が亡くなるとき)
オーナー社長が亡くなったときには
オーナー社長が保有していた企業の
株式は相続財産になります。
相続財産になった場合には
相続税の課税対象になります。
相続税の課税対象になったときは
相続税を計算するために株式の
金額を計算する評価を行います。
評価で使う基準は実務上では
財産基本通達になります。
会社の状況によって評価方法
が変わりますので財産評価に
明るい税理士に計算してもらう
ほうが無難です。
一般的に社歴が何十年もあると
1株1円くらいだったものが
100万円とかに化けてしまう
ことがあります。
亡くなってから対応しても
遅いためオーナー社長が亡くなる
前に株価を下げる工夫が必要になる
ことがあります。
対応方法としてはいろいろと
難しいことを含めればありますが
オーナー社長にはご退任して
いただき退職金を支給して
会社の財政状況を悪くすることで
株価を下げるのが手っ取り早い
方法になります。
しかし、社長への退職金は税法上では
なんでも自分で決めることができる
状況にあることから
しっかりした計算根拠などを
用意しておかないと税務調査で
不当に高額な退職金であるという
認定が行われてしまい
経費算入が認められないケースに
発展するリスクがあります。
実務上では退職金の計算は
税務調査である程度認められる
ようにするための対策も必要です。
編集後記
役員への退職金では過去の裁判例
判例などが積みあがっているものの
判然としない結論が導き出される
こともあったりして実務上の混乱を
助長していることがあります。
この点、計算根拠として今後
考えることができることは
同種同規模の法人に対する
退職金のデータを統計データなど
として処理を行って
退職金の金額において客観的な
データを用いた計算をする工夫が
必要になると考えます。
現実的にはエクセルを使った
統計データの処理を行って
下位、中位、上位の分布図を
基に退職金の金額を計算して
これに対応する役員退職金の
功績倍率や特別加算金で整合性を
とるといった手法が考えられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務