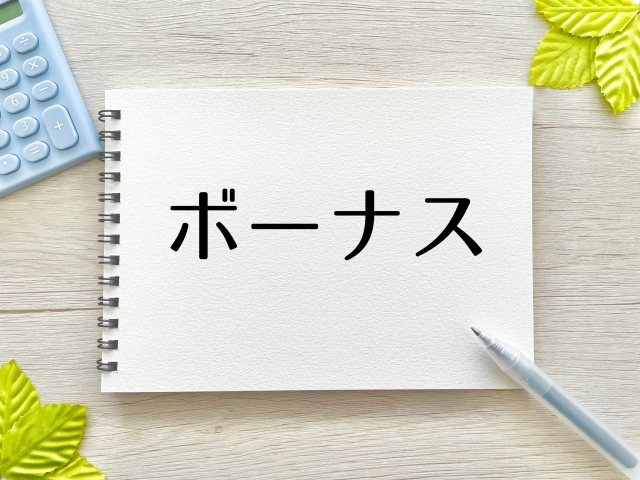【賞与と税金と社会保険】賞与、税金、社会保険の計算や定額減税も解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
賞与に焦点を絞った解説です。
それでは、スタートです!!
賞与はどのように計算されるのか?
以下2つで運用されるのが
一般的になります。
①賃金規定で定められた計算方法
②社長が評価などを加味して計算する方法
賃金規定はコンプライアンス
の観点から作成されることが
多いと思います。
日本では一般的にある程度の
規模がある会社が賃金規定で
給与や賞与に関するルールを
定めていることが多いと思います。
賃金規定では一般的に次のように
定められていると考えます。
①支給回数
②支給時期
③賞与支給日在籍要件(就業規則に書かれていることがある)
④賞与が支給される対象者
⑤支給算定期間
⑥支給しないこともある旨
⑦賞与の計算方法
以上のことが賃金規定に
書かれているわけです。
支給回数は年2回が一般的で
支給時期は夏と冬になりおおむね
6月と12月になっていると思います。
賞与支給日在籍要件は
賞与を支給する日に在籍している人に対して賞与を支給する
といったことが書かれています。
これは、賞与の支給算定期間に
在籍していれば賞与の計算上で
賞与が支給されることになります。
しかし、会社とすれば在籍して
これからも働いてくれる従業員へ
支給したいという思惑があるので
その旨を明らかにしているのです。
要するに、支給算定期間だけ
在籍して賞与の支給日にいない
従業員に賞与を支給しないように
するための文言です。
まずは賃金規定や就業規則を
確認しておくと安心だと思います。
中小企業の話に移ります。
中小企業は基本的に賃金規定
がないところが多いと思います。
なぜなら、中小企業の多くは
社長さんが売上をもってきて
会社が回っている状態が多いです。
この意味は、社長さんがすべてを
決める権限を持っていることが
多いので賞与に関しても
社長さんが独断と偏見で
決めていると考えられます。
一方、士業側から考えても
会社のルールを規定で定めると
中小企業の早い判断に影響が
ある可能性を考えます。
よほど必要性がなければ
賃金規定で余計なルールを
設けないと思います。
結果、どうなるのかというと
私のような税理士にほかの会社
は賞与をどうしていますか?
というご相談があります。
金額について具体的な話は
税理士からしませんが
会社の規模、支払能力を考えて
月給の2か月から3か月分を目安に
考えてはいかがでしょうか。
というような回答を税理士が
社長さんに行っていると思います。
賞与の税金と社会保険の計算と定額減税
賞与からは税金と社会保険が
差し引かれることになります。
税金とは所得税であり
賞与では源泉所得税が天引きされます。
賞与の源泉所得税は賞与が支給
される月の前月の月給を基に
計算されます。
具体的には
①前月の総支給額-前月の社会保険
②扶養人数
により賞与に対する源泉徴収額の算出率の表に当てはめて税率が決定されます。
賞与の算出率が出た後に
(賞与の金額-賞与の社会保険)×算出率=源泉所得税
計算されます。
次に賞与の社会保険になります。
次のように計算されます。
①健康保険:標準賞与額×保険料率×1/2
②介護保険(40歳以上):標準賞与額×保険料率×1/2
③厚生年金:標準賞与額×保険料率×1/2
④雇用保険:賞与の金額×6/1000(一般の事業)
保険料率は都道府県により異なります。
雇用保険は農林水産・清酒製造の事業、建設業では7/1000です。
標準賞与額は賞与の金額から
1000円未満の端数を切り捨てて
計算された金額です。
あまり一般的ではありませんが
毎年4月から6月までの類型の
標準賞与額が573万円を超えた
場合には
573万円が上限になり574万円
以降は健康保険と厚生年金の
対象金額から除かれます。
東京都だと39歳以下では
①健康保険料率:9.98%(個人負担分4.99%)
②厚生年金保険料率:18.3%(個人負担分9.15%)
になり
40歳以上だと介護保険が
加わり
①健康保険料率:11.58%(個人負担分5.79%)
②厚生年金保険料率:18.3%(個人負担分9.15%)
になります。
雇用保険と合わせると
20%超は少なくとも
社会保険として天引きされる
仕組みになっています。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
さて、このような計算をする
ことになるわけですが
令和6年6月からはすい星のように
定額減税という手取り額が増える
仕組みがあります。
本人や扶養親族になる人
1人当たり3万円になります。
6月に支給される給与と賞与
から適用されるのです。
定額減税の仕組みは給与や
賞与から天引きされる
源泉所得税から控除されます。
言い換えると、定額減税が仮に
18万円あったとしても
6月で給与や賞与から天引き
される源泉所得税が18万円に
満たなかった場合には
すべて使い切ることはできない
仕組みになっています。
では、6月で控除しきれなかった
定額減税はどうなるのかというと
7月以降に天引きされる
源泉所得税に適用して控除されます。
ここでも控除しきれなければ
8月、9月、10月・・・と
順次控除しきれなかった
金額が控除される仕組みです。
手取りが増えるといっても
源泉所得税が天引きされない
状態と同じですから
定額減税分の金額が一度に
手許に入るわけではないです。
賞与の支給日前に退職した場合に賞与は支給されるのか?
すこし込み入った話として
賞与の支給日前に退職した場合に
賞与が支給されるのかを考えます。
結論は就業規則に
賞与支給日在籍要件
がある場合には支給されません。
一方でこちらがない場合には
在籍期間分の賞与の支払い義務が
発生する可能性があります。
この場合はあなたと会社で
交渉するなどのトラブルが
発生すると考えます。
上記以外では年俸契約で
年俸を14か月で割って支給するなど
といったことを決めている場合は
会社に在籍していようがいまいが
会社には賞与の支払い義務が発生します。
これ以外にも会社が解雇した
などの場合のように
従業員の過失などがなくて
従業員が会社から去らねば
ならないようなときにも
会社には賞与の支払い義務が
発生する可能性が高いです。
こちらも会社は賞与を支給する
考えはないと思うので
トラブルに発展すると考えます。
編集後記
個人事業主になると賞与は
当たり前のようにありません。
スポットのご依頼があり対応すると
お金が入るのでこれが賞与のような
ものかもしれませんね。
賞与といえば決算賞与も考えられます。
会社の決算内容が良ければ
従業員に還元されるアレです。
中小企業では税金を支払うくらい
なら従業員へ還元したいと考える
社長さんも少なくないと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務