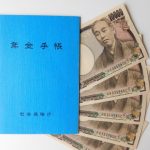【定額減税】給与明細への反映をしてみて気が付いたポイント
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
定額減税を給与明細に反映した
ことで気が付いたことを解説します。
それでは、スタートです!!
定額減税の給与明細への反映する4つの項目
①給与計算時点で判明している定額減税の金額
②減税額
③本来徴収するべき所得税
④実際の徴収された金額
給与明細では上記4つを明示
することになります。
定額減税の金額は給与計算
時点では見込みの金額です。
現時点で対象になる扶養親族
と本人分で計算された金額です。
減税額とは定額減税の金額
のうち今回の給与支給で
減税される金額になります。
本来徴収されるべき所得税
とは給与収入から社会保険料を
差し引いて計算された源泉所得税
になります。
実際の徴収された金額では
本来徴収されるべき所得税-定額減税の金額の差額
を書きます。
マイナスになる場合には
ゼロになります。
なぜこれらが表示される
必要があるのかは後述します。
給与明細を渡すときに説明するポイント
令和6年6月1日以降に
支給される給与明細を渡す場合は
定額減税についても説明をすること
が想定されるところです。
説明方法としては次のように
場合分けできます。
①定額減税で控除しきれず、7月以降に繰り越される場合
②6月支給分の給与で定額減税分をすべて使ってしまう場合
7月以降に定額減税が繰り越される
場合にはおいては
本来徴収されるべき所得税が
定額減税よりも少なかったため
6月支給分では控除しきれず
7月以降に定額減税の残りが
繰り越されます。
7月でも定額減税の残りが
控除しきれない場合には
8月以降に繰り越されて適用
されると説明できます。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
6月支給分で定額減税の金額
を使い切ってしまう場合には
本来徴収されるべき所得税が
定額減税よりも多かったため
徴収された所得税が少なくすみ
7月以降は本来の金額に戻る
ことになると説明できます。
もう一つ、説明のときに行って
おきたいことは
月給で適用される定額減税は
本人以外が見込みであるため
年末調整で定額減税の対象者に
ならない扶養親族と
月給の計算で見込みで適用した
扶養親族に違いがある場合には
年末調整で適用される定額減税
の金額に違いが生じることです。
年末調整時点で確定した
定額減税の対象扶養親族が
月給で適用した扶養親族より
増えた場合には定額減税は
増えることになり
年末調整では還付額が
増える可能性があります。
逆に年末調整で適用される
定額減税の扶養親族が
月給で適用された定額減税の
扶養親族より減ることになれば
定額減税の金額も減り
徴収になる場合があります。
人ごとに定額減税の繰越額を管理するのか?
国税庁では月給で適用した
定額減税について事績簿を
公表しています。
こちらは源泉徴収簿と連動した
帳簿になっています。
始めに給与明細に表示する
4つの項目を明示しましたが
4つの項目が事績簿の記載事項
になっています。
事績簿では定額減税の金額を
どのように適用したのかを
管理することができるように
なっています。
実務上で申し上げると
事績簿は作成が義務ではありません。
したがって、作成が不要であれば
作成しなくても問題はありません。
しかし、従業員の説明に使うとか
あとで定額減税についてどのように
適用しているのかといった
従業員の説明に対する答え
にしたい場合には作成しておく
とよいかもしれません。
編集後記
私は現状で事績簿の作成は
考えておりません。
給与計算ソフトで管理できること
月給時点では見込み適用であること
が理由になります。
最終的には年末調整で確定した
定額減税を適用して控除しきれない
金額が発生した場合には
源泉徴収票と給与支払報告書
の摘要欄に表示することで済む
問題ととらえています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務