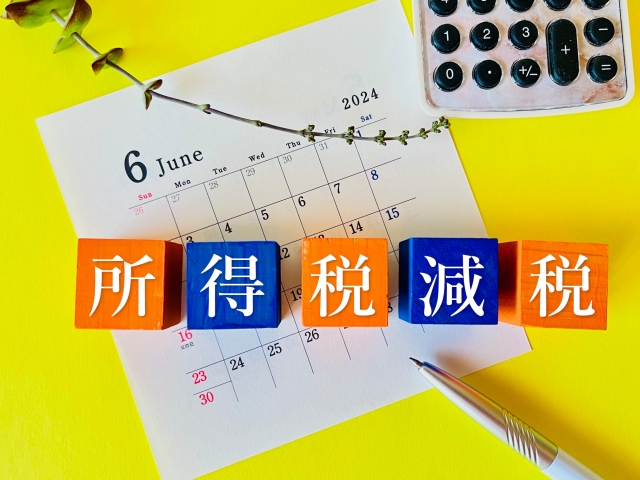【定額減税】年金と給与では2重適用が可能になることがある
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
定額減税が適用される年金と
給与では2重適用が発生する
件を解説します。
それでは、スタートです!!
定額減税の2重適用とは?
定額減税は適用対象者で
あれば自動的に適用されます。
現状では、令和6年6月以降の年金
や給与で適用されます。
このときに、給与で適用されれば
年金で適用されないとか
年金で適用されれば給与で適用
されないといったことはありません。
年金と給与でそれぞれ適用される
ということになります。
これが定額減税の2重適用
になります。
現行法令上では2重適用が
発生する制度になっています。
2重適用が確定申告義務にならないことが明らかに
国税庁は令和6年5月に公表した
令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)
にて
定額減税の重複適用をもって確定申告義務が発生しません
との見解を公表しました。
こちらは定額減税Q&Aの
2-3公的年金等の支払いを受ける給与所得者に対する定額減税
にアンサーに記載があります。
なぜこのようなことを書いたのか
というと次のように考えるからです。
公的年金等に係る確定申告不要制度
平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
要件を抜き出すと次の通りです。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
①公的年金等の収入金額が400万円以下であること
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
収入金額とは額面ですから
年金から控除される
介護保険料や源泉徴収税額
控除前の金額になります。
言い換えると額面が400万円以下
であることが必要です。
雑所得以外の所得金額とは
この記事では給与所得者で
年金をもらっていることという
前提になりますから
給与所得が20万円以下であること
と言い換えることができます。
給与所得が20万円以下になる
場合の額面は75万円になります。
給与所得の計算では額面から
給与所得控除を差し引いて
給与所得になります。
75万円ですから月給ベース
に直すと62,500円になります。
現実を考えるとほとんどの人は
年金と給与で確定申告をする
ような状況になるかと考えます。
というのは年金が少ない場合は
パートなどで生活費を稼ぐ都合上
月給62,500以上になるように
していることが考えられるためです。
2重適用であっても2倍の減税にならない可能性
2重適用だから定額減税の効果も
2倍になるのかというとそうでも
ないかもしれません。
給与収入で定額減税の適用対象者は
扶養控除等申告書を提出している
事業所で行われます。
すると月給62,500円の人が
控除される源泉所得税はゼロです。
つまり、定額減税を適用して
給与から控除される源泉所得税
を少なくしようと思ってもできない
というわけです。
では、年金から控除される
源泉所得税の計算は
(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×5.105%
になっています。
つまり、公的年金から源泉所得税
が控除されるためには
年金支給額>社会保険料+各種控除額
という状態である必要があります。
各種控除では最低でも13万5千円
が控除される仕組みのため
多くの人は源泉所得税がゼロ
になっていると考えられます。
結果、確定申告不要制度の対象者
になっている場合には
そもそも定額減税が控除される
源泉所得税が発生しない可能性が
高いのです。
結果、定額減税での減税効果はなく
給付金の対象になると考えられます。
編集後記
年金で400万円を超える人を
見たことは一度もないですね。
過去に300万円超えている人を
見た記憶はあります。
戦時加算など特別な何かが
加算制度で年金を受給していないと
現実では起こりえないのかなと
考えます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務