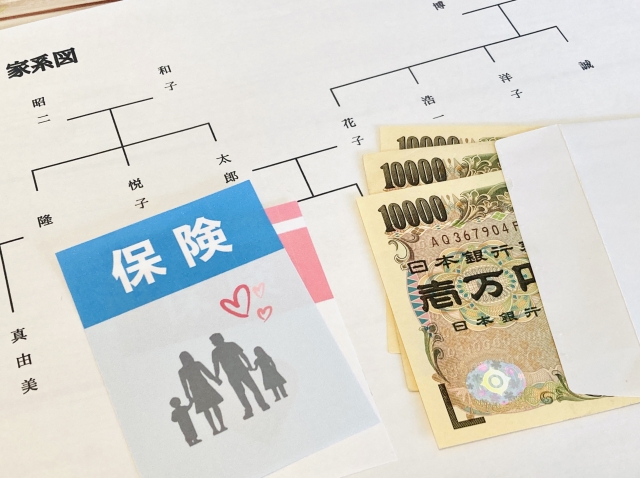【みなし相続財産】死亡保険金の取扱いを税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
みなし相続財産になる死亡保険金
について解説します。
それでは、スタートです!!
みなし相続財産とは
保険料を負担していた人が
亡くなったことをきっかけに
保険の受取人に保険料などが
払い戻されるものです。
イメージとしてわかりやすいのは
死亡保険金です。
夫婦関係で解説すると
保険料の負担者:夫
保険の受取人:妻
受け取ることができる保険:死亡一時金
この場合には夫が亡くなると
死亡一時金が妻に支払われる
ことになります。
夫が亡くなったことをきっかけに
妻に保険が下りたので
相続税では相続で保険をもらった
と考えます。
これがみなし相続財産と
呼ばれるものです。
死亡保険金の相続税の計算での取り扱い
結論から申し上げると
死亡保険金には非課税枠
というものがあります。
計算は以下のようになります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
対象者は
相続人(相続放棄者や相続権の失権者は含みません)
相続人が死亡保険金を受け取った
場合にのみ非課税枠の計算を使う
ことができます。
言い換えると相続人以外の人が
受取人になっている死亡保険金には
非課税枠は使えないです。
500万円に乗じている法定相続人の数
では相続人が入りますが
相続人の中に相続放棄者がいた
としても含めて計算して
よいことになっています。
なお、相続人の中に養子がいる
場合の法定相続人の数の計算では
実子がいる場合:1名
実子がいない場合:2名
まで含めてよいことになっています。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
死亡保険金は亡くなった人が
残された家族が困らないよう
自分に保険をかけておくという
ものでもあります。
しかし、相続税では相続税の
課税対象になってしまうという
ちぐはぐな取り扱われ方
になっているところです。
せっかく今後の生活費などの
ために使おうとしているところに
相続税が課税されてしまうと
税金負担分だけ生活費などに
使うお金が減ってしまいます。
こうしたことに対応するべく
非課税枠があると考えられます。
受取人以外の人が死亡保険金を受け取った場合
話は少し変わりまして
死亡保険金を受取人以外の人が
もらったケースを考えます。
以下のようなケースです。
保険料の負担者:夫(子からみると父)
受取人:子
受け取る保険金:死亡一時金
実際に受け取った人:妻(子からみると母)
このような場合の取扱いは
次のようになります。
死亡保険金の受取時の取扱い:子に対するみなし相続財産として処理
実際に死亡保険金を受けったときの取扱い:子が妻に対して贈与をしたとして処理
こちらは国税庁が公表している
No.4114 相続税の対象になる死亡保険金
から引用しています。
取扱いの考え方は
夫が死亡したことによって
受取人である子には
死亡保険金を受け取る権利が
自動的に付与されます。
したがって、この時点で
みなし相続財産になります。
しかし、実際に受け取ったのは
妻になるので
相続税法での考え方は
子がいったん死亡保険金を受け取り
そのあと、子が妻へ死亡保険金を
あげた(贈与)と考えます。
取引が2つになりそれぞれ
べつべつの取引として
取り扱うわけです。
編集後記
みなし相続財産になって
非課税枠が使えるのは
死亡退職金も同様です。
死亡後に受け取る退職金でも
親族の生活費などのために
お金が必要になるからです。
みなし相続財産では
申告書第9表と第10表を使って
計算することができます。
事前に一人当たりの非課税枠の
計算ができますので確認してみると
よいかと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務