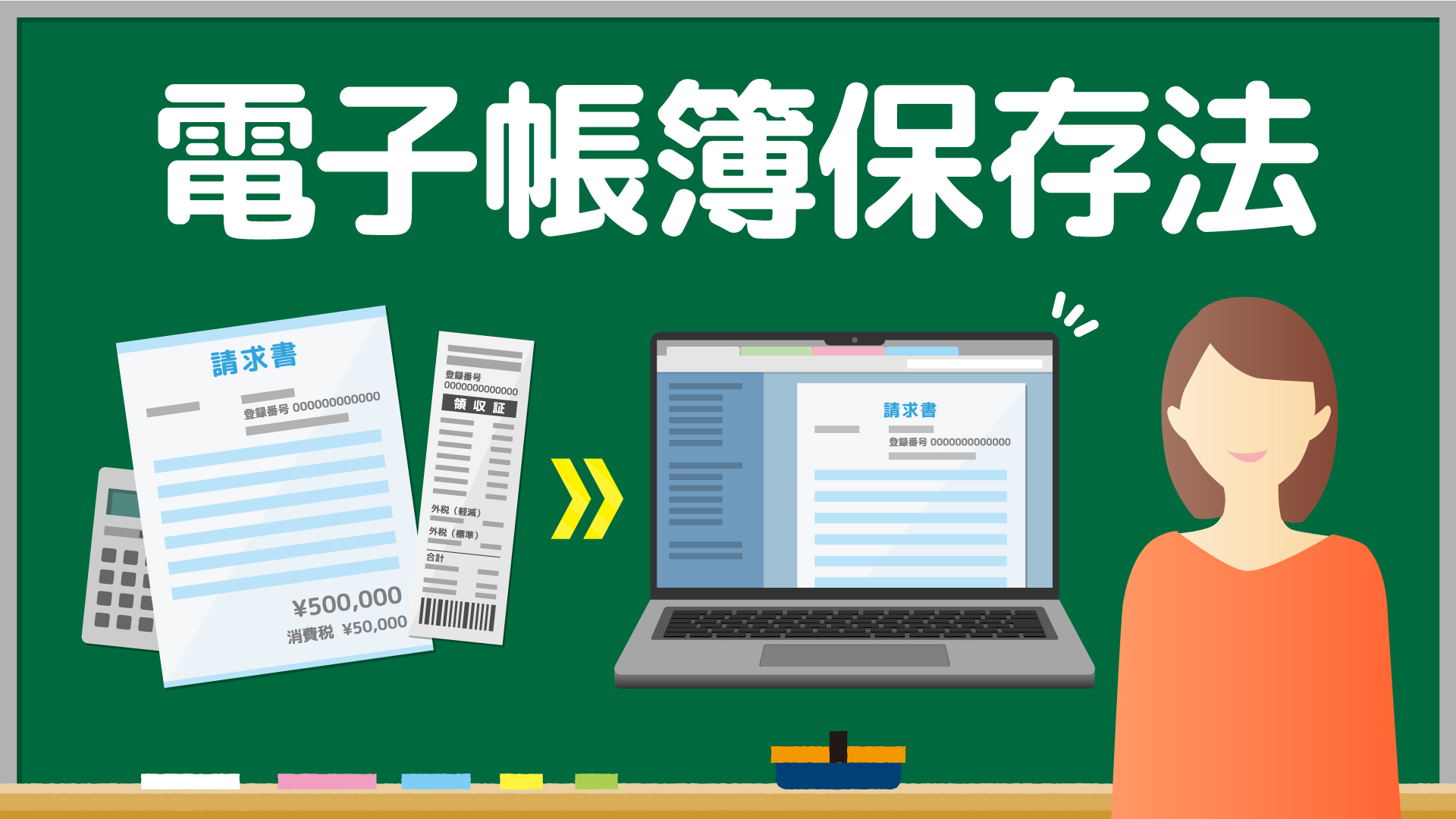【電子帳簿保存法改正】令和7年度改正内容を税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
令和7年度で改正された電子帳簿保存法
の内容を解説します。
それでは、スタートです!!
令和7年度の電子帳簿保存法の改正内容
令和7年度税制改正において
電子帳簿保存法の電子取引
について改正がありました。
請求書等のデジタルデータ(電子取引データ)を自動で保存し、帳簿に自動連係する仕組みに対応した制度
こういった仕組みを利用すると
以下の取り扱いになります。
・一定の要件を満たして送受信保存を行う場合には、電子取引データに関連する隠ぺい・仮装行為に対する重加算税の10%の住の適用対象から除外されます。
・また、青色申告特別控除65万円を適用することできることとされます。
一定のルールとは
①電子取引データの改ざん防止要件
データの送受信と保存を訂正削除の履歴が残るシステムや訂正削除ができないシステムで行う②適正記帳のための要件
・電子取引データの金額を訂正削除を行った上で電子帳簿に記録することができないこと(又は訂正削除の事実を確認できるようにしておくこと)・電子取引データと電子帳簿との関連性を相互に確認することができるようにしておくこと
税制上の措置を受けるためには
・国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用する
・上記の一定の要件を満たしていること
・あらかじめ届出書の提出を行うこと
税制上の措置が開始される期間
・重加算税の10%果汁の適用除外
→令和9年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税・青色申告特別控除
→令和9年以降の所得税
実際の取引を使ったシステムの流れ
実際の取引を使ったシステムの
流れを確認します。
どこで何を使って要件を満たすのか
ということがポイントです。
①電子取引データの送受信
→改ざん防止の確保②販売管理ソフトや証憑管理ソフトなどから会計ソフトへの連動
→記帳の適正性確保、電子帳簿との相互関連性確保
先ほど確認したように送受信と
保存についてルールがあります。
実際の取引ではあなたが受け取る
請求書などがあります。
このときにPDFをメールで受け取り
クラウドの証憑管理ソフトへ保存を
行ったとします。
このときに受信したことや保存
について訂正削除履歴が残るシステム
又は訂正削除ができないシステムを
使って改ざん防止の確保をします。
上記は、あなたが発行した請求書等
の送信と保存についても同じです。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
ここまで第一段階の要件になり
次に受領した請求書等は
証票管理ソフトへ保存することで
会計ソフトへ自動連係される仕組み
が整っていることとします。
弥生会計とスマート証憑管理との
連携をイメージすることになります。
自動連係で記帳が行わるときに
電子取引データの金額を訂正削除を
行った上で電子帳簿に記録することは
できないこと
又は訂正削除の事実を確認できる
ようにしていることが求められます。
要するに自動仕訳で会計ソフトに
記帳する場合には
金額の修正ができないとか
金額の修正ができる場合には
その履歴が確認できるように
されている必要があります。
さらに証憑管理ソフトと会計ソフト
との間でPDFなどのデータと
会計ソフト上の帳簿の関連性を
相互に確認できるようにしておく
ルールがあります。
デジタルデータを使うことで事務負担軽減になるのか?
私見になりますが大量のデータを
一気に処理するような場合には
デジタルデータを活用した
自動連係機能にて一気通貫で
処理することで
事務負担軽減や会計処理
資料の整理に関する時間の減少
といったことが期待できると
考えます。
大量ではなく処理するデータが
限られている場合には
データ保存と会計処理は切り分けて
それぞれで処理をしたほうが
事務負担の増加は少なくなる
と考えます。
令和7年度の電子帳簿保存法における
自動連係機能を使う場合の改正の
前提は
大量のデータで処理することになる
会社や個人に対してメリットを与える
ものになります。
個人では今回の改正を適用する
ことで青色申告特別控除が65万円
になるとしても
電子申告することでも
青色申告特別控除は65万円なので
大量のデータを想定できない
個人にあっては現状で適用する
メリットは薄いです。
また、法人についてもいちいち
データを改ざんするなどして
脱税になってしまうような対応
をするのかなと考えます。
編集後記
私はスマート証憑管理を使って
データを保存しており
仕訳データの作成までをしている
ことがあります。
自分の処理に使える時間があれば
このようにするのですが
時間がない場合にはデータの
保存だけにして
会計ソフトへの入力は手入力
にしています。
大量のデータがあれば自動連係
ほど頼もしい機能はないのですが
現状だと業務を圧迫するだけの
処理になってしまうのが残念です。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務