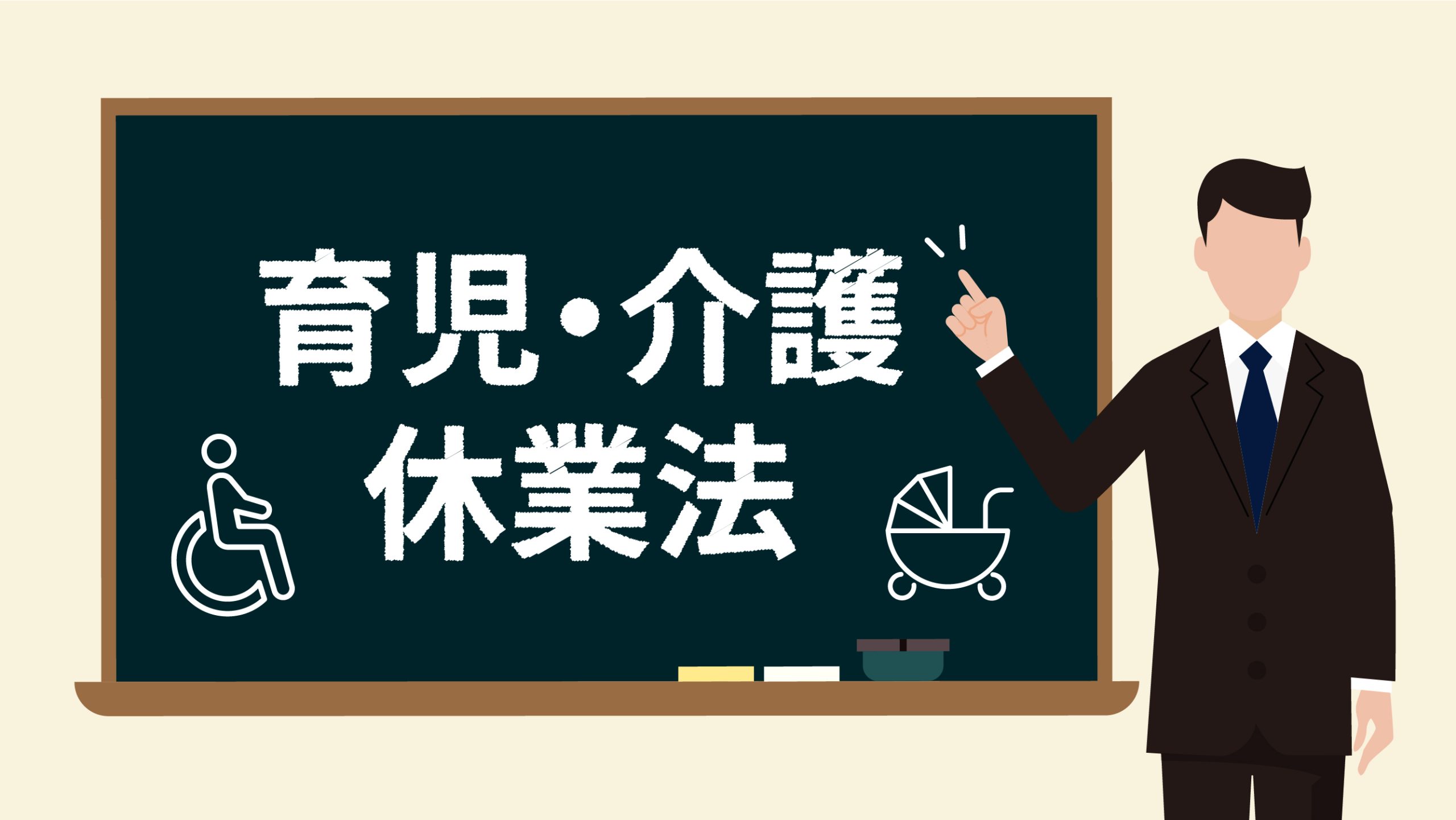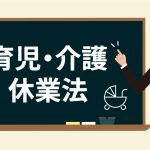【育児介護休業法改正】令和7年10月から適用されるものを社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
育児介護休業法の改正で
令和7年10月から適用される
内容を解説します。
10月からの改正は育児だけ
追加された制度です。
それでは、スタートです!!
柔軟な働き方を実現させるための措置
・育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知、意向確認
が追加されます。
まずは、育児期の柔軟な働き方を
実現させる措置を確認します。
対象労働者
3歳から小学校就学前の子を育てている労働者
会社が行う措置
次の中から2つ以上の措置を選択して講じなければなりません。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を育てることを容易にするための休暇の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度
②と④は、原則時間単位で取得可にする必要があります。
上記の選択できる措置の詳細
は以下の通り
①終業時刻等の変更(次のいずれかの措置で1日の所定労働時間を変更しない)
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)②テレワーク等
1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できるもの③保育施設の設置運営等
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの
(ベビーシッターの手配および費用負担など)④養育両立支援休暇の付与
1位日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの⑤短時間勤務制度
1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの
養育両立支援休暇とは
就業しつつ子を育てることを容易にするための休暇
を指します。
次に柔軟な働き方を実現するための
措置の個別の周知・意向確認を
確認します。
対象労働者
3歳未満の子を育てている労働者
行う時期
子が3歳になるまでの適切な時期
会社が行う措置
会社が育児期の柔軟な働き方を実現するための措置で選択した制度に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を労働者ごとに個別におこなわなければなりません。
一応、利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められないことになっています。
周知時期
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日~2歳11か月に達する日の翌日まで)現実には、2歳の子を育てている時期に行うことになると思います。
周知事項
①会社が選択した対象措置の内容
②対象措置の申出先(例えば、人事部など)
③残業免除・時間外労働や深夜業の制限に関する制度
個別周知・意向確認の方法
面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかです。
面談はオンラインでも可能、FAXや電子メール等は労働者が希望した場合のみ可能です。
会社の望ましい対応としては
家庭や仕事の状況が変化することを前提に、労働者が選択した制度が適切であるかを確認することを目的に、定期的に面談を行うことが推奨されています。
仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取・配慮
・妊娠、出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
・聴取した労働者の意向についての配慮
が追加された内容です。
まずは、個別の意見聴取から
確認します。
意向聴取の時期
①労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
②労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)望ましい対応としては、上記以外の他、育児休業後の復帰のときや労働者から申し出があったときなどにも実施することとされています。
聴取内容
①勤務時間帯(始業および終業の時刻)
②勤務地(就業の場所)
③両立支援制度等の利用時間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
意向聴取の方法
面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれかです。
面談はオンライン可であり、FAXや電子メール等は労働者が希望した場合のみ可です。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
聴取した労働者の意向についての
配慮を確認します。
会社が行わなければならないこと
上記で確認した労働者から聴取した仕事と育児の両立の意向について、自社の状況に応じて配慮をしなければなりません。
具体的には労働者の意向により
以下の配慮をします。
・勤務時間帯や勤務地にかかる配置
・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整
・労働条件の見直し
望ましい対応としては
・子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
・ひとり親になっている場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること
労働者に仕事と育児を両立してもらうための考え方
中小企業にとっては今回の改正は
厳しい内容かと思います。
なぜなら、万年人手不足である
中小企業における工数が減って
しまう恐れがあるためです。
この中でいかにして従業員に
仕事と育児の両立をしてもらうのか
を考えることになります。
今回の改正のポイントは事業者が
労働者に対する対象措置を決める
ことができることです。
始業時刻等の変更から短時間勤務制度
まで中から最低2つを選択します。
従業員の仕事内容によって
選択しやすいものがあるはずです。
事務職で事務所以外でもできる
といった場合にはテレワークが
選択になります。
工数は減りますが養育両立支援休暇
は1年間に10日付与するだけなので
導入するハードルは比較的低い
措置かもしれません。
お金に余裕があればベビーシッター
の手配と費用負担もよいかと思います。
ただし、会社が費用負担をすると
社会保険や税金の課税対象になるため
実際には従業員に優しい措置では
ない可能性があります。
以上のことから現実的な対応も
含めたハードルが低い順番を
格付けしていくと
①テレワーク
②養育両立支援休暇の導入
③始業時刻等の変更
④短時間勤務制度の導入
⑤保育施設の設置運営等
になるかと考えます。
基本的には産前産後休業があり
育児期間が想定される中で
育児を行っている従業員には
少なくとも残業免除になります。
また、近年にあっては男性の育休
取得率も高まっている傾向があるので
女性だけが育児をするという
わけではありません。
売上、資金繰り、人の手配などに
さらに既存従業員の退職防止策
として対応を迫られている制度
と言えます。
編集後記
改正では基本的に義務規定が多く
会社は対応しなければなりません。
全く対応しないというのは
ナンセンスであり
単なる法令違反企業というレッテル
が張られるだけ外部からの信用失墜
につながると考えられます。
逆に、制度の内容を理解して対応
するだけで法令に対応している会社
との印象を外部へ与えることが
できます。
育児対応だけ取り出してみると
今後はくるみん認定を通じて
法人税法上の優遇措置があり
所得拡大促進税制の上乗せ措置
との相性もよいと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務