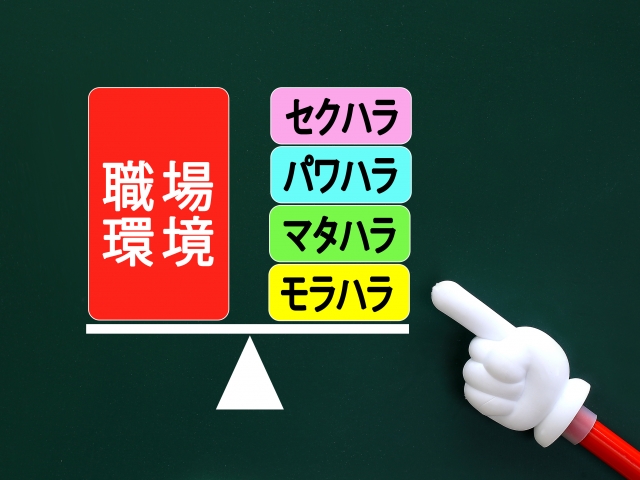【職場のハラスメントに関する実態調査】の報告資料から事業者の対応を解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
厚生労働省が公表した
職場のハラスメントに関する
実態調査を確認しつつ
事業者の対応を解説します。
それでは、スタートです!!
職場のハラスメントに関する実態調査とは?
調査の目的は
職場におけるハラスメント対策に取り組む企業やハラスメントを受けている労働者の状況も変化していると考えられることから、企業におけるハラスメントの発生状況や企業の対策の進捗、労働者の意識等を把握し、今後の諸施策に反映させることを目的に、実態調査を実施することとした。
令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書から抜粋
企業と労働者の2つから
アンケートを取っています。
企業の調査対象は全国の
従業員30名以上の企業と団体
になっています。
労働者の調査対象は全国の
企業団体に勤務する20歳から
64歳の男女労働者になり
経営者や自営業者を含んだ
役員も入っています。
特別サンプル調査では
・女性の妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
・男性の育児休業等ハラスメント
・就活等セクハラ
調査報告書では現状でのハラスメント
の発生と事業者が行っている対応
についてまとめられています。
近年問題が表面化してきた
カスタマーハラスメントについても
調査が行われています。
以下、ハラスメントの名称は
略称を使用します。
調査報告書の結果からハラスメントはどうなっているのか?
数字を細かく読み解くよりも
何が起こっているのかを確認します。
まずは、企業調査結果として
ハラスメントの発生状況と
取り組み状況を確認します。
令和2年に前の調査があったため
今回は令和5年までの過去3年間の
状況になります。
以下、労働者調査でも同様です。
ハラスメントの状況
①ハラスメントの相談件数
・セクハラ以外では件数は変わらないが最も高い
・セクハラにも減少しているが最も高い
・カスハラのみ件数が増加している割合が減少している割合より高かった
・カスハラ以外は相談件数が減少しているが増加している割合より高かった②相談件数の多かった業種
・マタハラなど
→金融業、保険業、教育、学習支援業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉、生活関連サービス業、娯楽業が多い傾向だった・カスハラ
→医療、福祉、宿泊業、飲食サービス業、不動産業、物品賃貸業の順に相談が多い傾向だった・就活等セクハラ
→電気・ガス・熱供給・水道業、宿泊業、飲食サービス業、育、学習支援業の順に相談が多い傾向だった
ここでわかることはセクハラは
一般的にやってはいけない行為
として認知されていると考えらえます。
マタハラや育児・介護休業の
ハラスメントも認知度が向上
していると考えられます。
ただし、女性が多く就業する業種
についてはセクハラなどのハラスメント
行為が発生しやすい状況と考えます。
特に、ハラスメント性向が高い
業種は相談件数の多かった業種の
3つすべてに上がっている
宿泊業と飲食サービス業
になります。
カスハラでは対個人相手に事業
を行っている業種について発生する
可能性が高くなっていると考えられます。
ハラスメントへの取り組み
・相談窓口の設置と周知をしている割合が最も高く、7割以上の企業が実施している。
・ハラスメントへの内容、ハラスメントをなくす旨の方針の明確化と周知・啓蒙の割合も高く、6割以上の企業が実施している
・業種別では、いずれのハラスメントおいても、金融業、保険業、複合サービス業などで取り組みをしている割合が全般的にほかの業種よりも高かった。
・カスハラでは、一般消費者との接触が高い業種などにおいて取り組みを実施ている割合が高い
・カスハラが起きやすい業種の企業では、取り組みを進めるうえでの課題は迷惑行為に対応する従業員等の精神的なケアが難しいとの回答が他の業種よりも多かった。
・就活等セクハラでは、金融業、保険業、情報通信業などで各取り組みの実施割合が他の業種よりも多かった。
以上のことからわかることは
アンケートに回答した企業では
相談窓口の設置はおおむね
行っていることになります。
次いでハラスメントの研修などで
内容や啓蒙も行っています。
企業においてもハラスメント
への取り組みをしているものの
残念ながら一定のハラスメントは
発生していることが明らかに
なっている状況が明確になりました。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
話は変わりまして労働者等
調査結果のまとめを確認します。
労働者におけるハラスメント
被害を受けた経験
①ハラスメントの被害割合
→パワハラ19.3%、セクハラ6.3%、カスハラ10.8%になっており、カスハラを経験した割合が高い業種は、生活関連サービス業と娯楽業で16.6%、卸売と小売業で16%、宿泊業と飲食サービス業で16%の順で高かった。②勤務先の蓮面との予防・解決の取り組み評価
→パワハラで積極的に取り組んでいると回答した者で、ハラスメントを経験した割合は15.2%で最も低く、あまり取り組んでいないと回答した者では35.1%が経験したとして最も高かった
セクハラとカスハラでは勤務先が取り組んでいると回答して者でハラスメントを経験した割合がそれぞれ5.5%と12.2%で最も低かった③ハラスメントを受けた後の行動
→何もしなかったが最も多く、カスハラでは社内の上司に相談したが最も多かった。
ハラスメントの予防・解決に向けた取り組みの評価が高いほど、社内の同僚や上司に相談した割合が高く、何もしなかったの割合が低かった。
上記からわかることは一定程度
ハラスメントは発生してしまう
ことです。
ただ明るいい兆しもあります。
勤務先がハラスメントに積極的
に取り組んでいる場合には
ハラスメントを受ける割合が
低くなる傾向があることです。
逆にあまり取り組んでいない場合は
ハラスメントを受けたと回答している
割合がそうではない勤務先の労働者と
比べて2倍になっています。
これは、労働者の行動性向にも
現れていることになります。
ハラスメントに対する
勤務先の対応
①勤務先が認識しているハラスメントの割合
パワハラ37.1%、セクハラ23.9%、カスハラ59.2%②ハラスメントを知ったとの勤務先の対応の割合
→パワハラとセクハラで特に何もしなかったが最も高く、カスハラでは要望を聞く、相談にのってくれたが最も高かった。③勤務先のハラスメント認定
→パワハラとセクハラでは、ハラスメントがあったともなかったとも判断せずあいまいなままだったが最も高かった
上記でわかることは
勤務先はハラスメントを認識
している割合とハラスメントの
被害割合に齟齬があることです。
ここから想像するにハラスメント
を受けた本人が過少に申告している
可能性があります。
パワハラとセクハラについては
勤務先の認定が難しい場面が
あるかもしれません。
というのは、何もしなかったや
あいまいにされてしまったという
ことが最も高いためです。
従業員が多くなればなるほど
企業内での政治がまん延したり
主張がより通る可能性があるため
なかなか認識が難しくなるといった
ことが考えられます。
事業者がハラスメントにどう対応するのか?
以上のことから事業者がハラスメント
に対応することがなんとなくわかって
くると考えます。
まず、事業者としてやることは
・ハラスメントの相談窓口の設置
・ハラスメントの内容、ハラスメントをなくす旨の方針の明確化と周知・啓蒙
になると思います。
どちらもアンケートに回答した
企業の半数以上が行っている
取り組みになります。
もし、あなたがこういった取り組み
をしていない場合には
早急に取り組みを行う必要が
あると考えます。
上記2つの取り組みをしていても
一定の件数のハラスメントは
発生してしまいます。
しかし、パワハラに積極的に
取り組んでいる勤務先では
ハラスメントにあった割合が
低くなる傾向がありますので
あなたはハラスメントに積極的に
取り組むことでハラスメントの
被害割合が下がると考えられます。
積極的に取り組む内容としては
・ハラスメントの相談窓口の設置
・職場環境の改善のための取り組みとして適正な業務目標の設定、過剰な長時間労働の是正
・カスハラでは対応マニュアルの作成や研修の実施
になります。
特に、労働者側から挙がっている
実施したほうがよい具体的取り組みでは
職場環境の改善のための取り組みとして適正な業務目標の設定、過剰な長時間労働の是正
の割合が最も高いです。
編集後記
ハラスメント対応は少しずつ
やっていくことがよいです。
一気に全部をやろうとすると
事業利益との相反する取り組みに
なる可能性が高いためです。
例えば、相談窓口の設置は
お金はかかりません。
窓口を社内につくって
相談できる環境を用意するだけ
になります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務