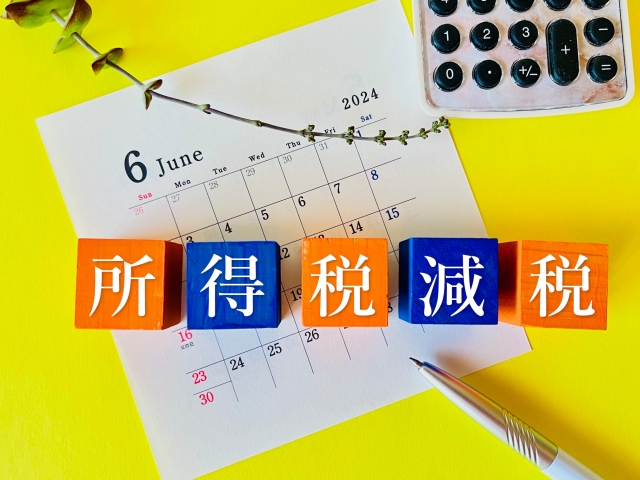【定額減税】給与明細に記載義務の閣議決定で定額減税の処理負担を最小限するポイント
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
定額減税が給与明細への記載される
義務による処理負担軽減のポイントを
解説した記事になります。
それでは、スタートです!!
定額減税の処理負担を軽減するポイント
令和6年5月21日の閣議決定で
定額減税の給与明細への記載義務
が決まりました。
これにより本来であれば
年末調整で定額減税をすべて
精算すれば済むところ
令和6年6月1日以降の月給や
賞与で定額減税を反映させる
ことが義務になりました。
実務上では、定額減税の処理は
給与明細に反映させる必要がある
ため事務負担の増加が懸念されています。
さて、事務負担の軽減策として
以下ポイントを解説します。
結論
月給や賞与の処理では本人分だけの定額減税を反映させるだけにとどめる
このようにすれば本人1名だけの
定額減税分3万円だけ反映させて
処理することができます。
実務上では定額減税の処理に
あたって
源泉徴収に係る定額減税のための申告書
の提出が必要です。
こちらは年末調整で提出される
扶養控除等申告書
に記載されることがない
扶養親族を確認するために
提出することになります。
しかし、本人分だけを反映させる
という方針で定額減税を処理する場合
こちらは必要ありません。
本人に適用される定額減税は
年収が確定していませんから
必ず定額減税を適用する必要がある
処理になります。
したがって、本人分だけ定額減税を
適用するようにすれば
3万円だけの定額減税を適用して
あとは年末調整で適正な定額減税
を適用すれば済むことになります。
月給や賞与に本人分だけで問題がない法的解釈
さて、定額減税が適用される場合に
月給や賞与での反映で本人だけ
反映して問題ないかどうかを検討します。
定額減税の根拠法令は
所得税法第41条の3の3
に規定がされています。
では、月給や賞与で定額減税を
適用するときに本人分だけの
反映で問題がないと解釈できる
根拠は
所得税法第41条3の3第3項
になります。
所得税法第41条3の3第2号の場合において、その者が同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
財務省 令和6年法律第8号より抜粋(一部、筆者加筆)
こちらをわかりやすくすると
同一生計配偶者又は扶養親族になるかどうかの判定は令和6年12月31日になる
と書いていることです。
言い換えると月給や賞与で
定額減税を適用する場合に
同一生計配偶者又は扶養親族分は
確定しておらず見込みになります。
実務上での運用解釈をすると
次のようにも解釈できます。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
令和6年11月までは同一生計配偶者又は扶養親族かどうかわからないので反映させていない
と解釈するわけです。
月給や賞与で同一生計配偶者又は
扶養親族を見込みで適用する
運用になるため
同一生計配偶者又は扶養親族
について見込みで適用できないと
考えることもできます。
このように解釈を行うことで
月給や賞与で定額減税を適用する
場合には
本人分だけの定額減税のみ
反映を行うという事務処理軽減
を行うことが可能になります。
また、従業員には同一生計配偶者又は
扶養親族は12月末で判断するため
定額減税は適用できないし
もし見込みで適用して
年末にやっぱり同一生計配偶者
又は扶養親族にならなかったら
年末調整で還付にならない
可能性があると説明すればよい
と考えます。
定額減税は年末調整で調整すれば済む
法律論では定額減税の対象者に
なる同一生計配偶者又は扶養親族
は令和6年12月31日で判断します。
ということは年末調整の書類に
書いてもらうときに
一緒に同一生計配偶者又は
扶養親族も把握すれば済みます。
このときのポイントは
年末調整に係る定額減税のための申告書
で扶養控除等申告書に書かれない
人を確認することです。
これで年末調整事務において
通常の年末調整を行って
年末調整の定額減税である
年調減税欄に金額を書けば
正確な定額減税が適用できます。
要するに、月給や賞与で把握して
年末調整でも把握するため
二度手間になるところ
年末調整のときに同一生計配偶者
又は扶養親族を確認するだけで済む
方法になります。
このようにすることで年末調整
の事務処理の中に定額減税の
処理を入れ込むだけで済むため
事務処理負担の軽減ができると
考えます。
編集後記
私はどのように定額減税を処理
しようかなと考えていて
今回のような方法を思いつき
6月以降の給与や賞与処理では
本人分だけの定額減税を適用
年末調整で本来の定額減税を
適用にします。
そもそも今回の閣議決定は
国の私的な取引への介入です。
給与は役員であれば委任契約
従業員であれば労働雇用契約が
会社と締結されています。
このときには会社から個人へ
支給される金品は給与になり
その給与の内訳が書かれているのが
給与明細になります。
給与明細に定額減税を記載させる
義務を事業主に負わせるという
ことは個々人との契約に対する
国の越権行為になります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務