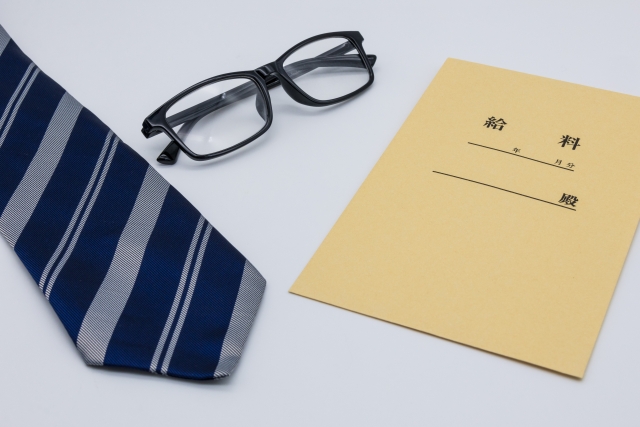【給与と食事チケット】課税と非課税について解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
食事手当又は食事チケットを支給
した場合の給与の課税・非課税
について解説をします。
それでは、スタートです!!
食事手当として金銭で支給すると給与課税
食事手当は給与の支給項目の
1つとしてあります。
食事手当は金銭で従業員へ支給する
支給項目になりますので
給与課税
されます。
給与課税の意味は
・源泉所得税
・住民税
・社会保険
・雇用保険
といったものの課税対象になる
ことです。
会社が福利厚生目的として
従業員によかれと思って支給
したとしても
税金などの課税対象になってしまい
食事代に見合わないことになる
可能性はあります。
食事チケット支給した場合の非課税にする方法
食事チケットとは
特定の飲食店を利用できるチケット
になります。
会社が食事チケット会社と契約して
食事チケットを従業員へ支給して
ランチ代に充ててもらう仕組みです。
こちらも会社が従業員になんの負担も
負わせることなく支給すると
給与課税
されることになります。
しかし、以下の条件を満たすことで
給与課税されない仕組みがあります。
役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。
なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
要するに月7,000円の食事チケット
を支給して3,500円を給与から控除し
従業員に負担してもらえば
給与課税されない
という仕組みです。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
福利厚生目的の理にかなっている
食事チケットになりますが
一方でデメリットのようなものが
発生してしまう可能性はあります。
例えば、
・周りに飲食店がないため食事チケットを支給しても意味がない
・お弁当を前提にしている従業員には支給の意味がない
といったことになります。
食事チケットを導入する場合には
会社の従業員の使用状況とか
会社がある飲食店の状況を確認して
導入するかどうを検討する必要はある
と考えます。
食事チケットを支給した会社のメリット
会社が福利厚生目的以外に発生する
食事チケットを支給した場合の
メリットを確認します。
・会社の負担は半分で済む
・一元管理ができる食事チケット業者を使うと管理が楽になる
・食事チケットのうち管理手数料は消費税の仕入税額控除ができる
・従業員の囲い込みになる可能性がある
といったことです。
先ほども申し上げたように
半分は従業員に負担をしてもらう
性質の都合上
会社が全額負担ではなく半分を
負担するため財政に優しいです。
食事チケットは従業員ごとに管理を
行う必要がありますが
食事チケットを管理できるツールを
提供している業者もあります。
こちらを使うことで会社の総務部の
負担を増やさない工夫もできます。
食事チケットの購入時には
食事チケット本体と発行手数料の
2つが請求されることがあるようです。
このうち、食事チケットは消費税の
仕入税額控除の対象にはなりませんが
発行手数料は仕入税額控除の対象に
なるので食事手当よりも消費税の
減税効果が見込めます。
中小企業でも食事チケットを支給
することは可能であるため
会社の規模に関わらず食事チケットで
従業員の囲い込みができる可能性が
あります。
編集後記
日本の税金や社会保険の課税体系は
会社が従業員に金銭や現物支給すると
給与課税される仕組みになっています。
食事チケットでは給与課税されない
ための方策として機能しており
ある程度の財政がある会社であれば
大きな負担なく導入できて便利だと
考えています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務