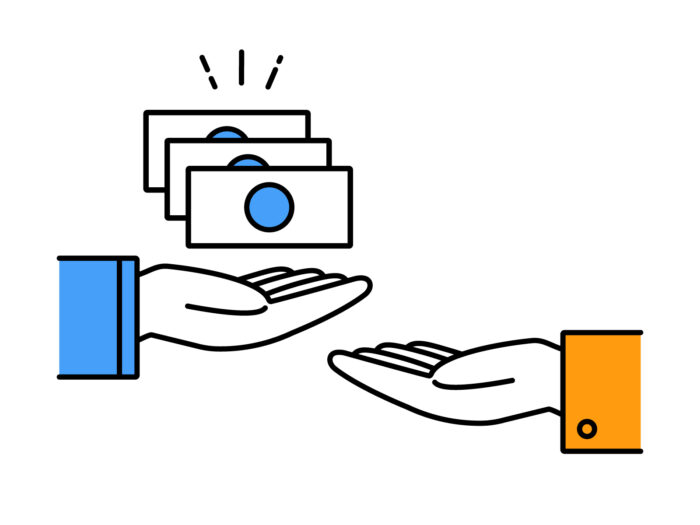【財産をもらったとき】どのような手続きになるのかを税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
財産をもらったときについて
基礎的な手続きを解説します。
それでは、スタートです!!
財産をもらったときには贈与税の手続きになる
財産を個人からもらったときは
贈与税の課税対象
になります。
贈与税の申告は年1回で
当年度の贈与税の申告と納付を
翌年2月1日から3月15日まで
に行います。
贈与の都度、1つ1つ個別に
行うのではなくて
当年度でもらった財産の合計を
計算して贈与税の申告をします。
令和7年を当年度と仮定すると
令和7年でもらった財産すべて
について
令和8年2月1日~3月15日までに
申告と納付をします。
贈与税の計算方法は2つ
・暦年課税
・相続時精算課税
という方法があります。
暦年課税は誰からもらった
としても使うことができる
計算方法になります。
相続時精算課税は親子や
祖父母から孫への贈与といった
親族間で行われる一定の贈与
について暦年課税に代えて
選択できる計算方法です。
相続時精算課税は一度選択すると
暦年課税で計算することが
できなくなるので慎重に検討する
ことが必要になると考えられます。
暦年課税の計算方法は
以下のようになります。
①当年度でもらったすべての財産の合計額-110万円=贈与税の課税対象金額
②①×課税対象金額の枠に応じた税率-控除額=納付する贈与税額
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
したがって、当年度でもらった
すべての財産の金額の合計額が
110万円よりも低いのであれば
申告は不要になります。
相続時精算課税の計算方法は
以下のようになります。
①当年度でもらった財産の金額の合計額-110万円ー2,500万円=贈与税の課税対象金額
②①×20%=納付する贈与税額
したがって、当年度でもらった財産
の金額の合計額が2,610万円以下で
あれば納付税額は発生しません。
しかし、申告に関しては以下の様に
分かれます。
①110万円以下の贈与で課税対象金額がゼロの場合:申告は不要
②110万円と2,500万円の合計で課税対象金額がゼロの場合:申告必要
相続時精算課税の2,500万円は
特別控除と呼びますが
こちらは使うごとに目減りします。
つまり、相続時精算課税で計算都度
2,500万円が控除されるのではなく
2,500万円のうち使った金額は
翌年になくなります。
令和7年で特別控除のうち300万円
を使うと令和8年の特別控除は
2,200万円になるという仕組みです。
特別控除は使う都度減っていき
最終的に特別控除の金額はゼロ
になるといった感じです。
贈与は相続のときに相続税の課税対象になる
贈与税の計算については
亡くなった人からもらった財産は
計算方法ごとに以下のように
相続税の課税対象になります。
暦年課税の場合
①令和8年12月31日までに発生した相続:死亡した日から遡って3年前の日から死亡の日までの間の贈与
②令和9年~令和12年までに発生した相続:令和6年1月1日から死亡の日までの贈与
③令和13年以降で発生した相続:死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間の贈与
相続時精算課税の場合
相続時精算課税で申告した贈与財産すべて
になりますが・・・
相続時精算課税を使っていた
としても110万円以下で済んでいた
贈与は相続税の課税対象になりません。
実務上で発生するのは
相続が発生する前に行った
贈与税の申告書の控えがなく
税務署に閲覧請求をしなければ
ならなくなるといったことです。
相続税の申告のときに
困らないように
贈与税の申告書の控えは
必ず保存しておくとよいと
考えられます。
編集後記
因みに法人からもらった財産は
所得税の課税対象になり
一時所得に分類されること
になります。
一時所得の計算ではもらった金額
から控除できる特別控除が50万円です。
相続時精算課税のように使った
金額がなくなる仕組みではなく
毎年50万円が復活して使う
ことができます。
したがって、法人から贈与を受け
その年の一時所得に分類される
金額が50万円以下であれば
所得税はかからないですし
申告も必要がないことになります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務