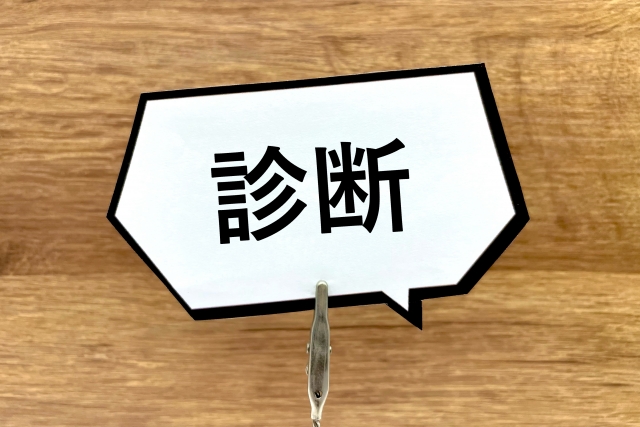【職業診断と判断】job tagでやりたいこと自分に合った職業の判断をしてみる
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
厚生労働省が公表している
職業の総合サイトjob tagを
解説します。
それでは、スタートです!!
job tagとは
職業情報提供サイト(job tag)は、「ジョブ」(職業、仕事)、「タスク」(仕事の内容を細かく分解したもの、作業)、「スキル」(仕事をするのに必要な技術・技能)等の観点から職業情報を「見える化」し、求職者等の就職活動や企業の採用活動等を支援するWebサイトです。
job tagより抜粋
基本的にはこれから働く人の
ための職業判断サイトです。
Top画面では個人での利用として
・適職を知る
・職業を検索する
・業種や職種を知る
・求職活動をする
から構成されています。
特に自分に合う職業を知りたい
では以下の5つの観点から
職業を特定するツールがあります。
・職業興味検査
・仕事価値観検査
・職業適性テスト(Gテスト)
・しごと能力プロフィール検索
・ポータブルスキル見えるかツール
これらのうちGテストを
やってみました。
現時点では言語・相談関係が
最も近い職業という結果でした。
言語相談関係では税理士も
職業の1つにあったので
現状の自分は適職にあった
仕事をやっていると確認できました。
自己診断ツールでやりたい職業を判断する
自己診断ツールでは先ほどの
Gテストなどを試して
やりたい職業の判断をする
ことができます。
テストや思っていることなど
で現時点でのあなたの状態に
あった職業が表示されます。
自己診断ツールが終わると
適職のようなものを確認
できるわけですが
あくまでも現時点の適職
のようなものです。
複数の職業が表示されるので
その中で興味がある業種や
職業を確認してみます。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
詳細では必要なスキルや
実際に行っている業務を
確認することができます。
試しに税理士のタスクを
表示させて確認しました。
実施順に表示されており
大まかな仕事内容を確認する
ことができます。
例えば
個人や企業から依頼を受け、税金の申告・申請・不服申立てなどの手続きの代理を行う。
というのが1位になっています。
実施率をもとに確認してみると
帳簿作成や指導助言といった
日々の業務についても
書かれており実態に沿った
評価がされていると感じました。
就業する方法を確認する
仕事の詳細を開くと
就業するには?
という項目が表示されます。
ここでも税理士で書かれた
内容を確認してみると
書かれている内容は
間違っていないのですが
現状とは少々異なる内容が
書かれていたりします。
税理士として実務修習を積んだ後、個人事務所を開業するケースがほとんどである
とされている表示です。
「ほとんど」というのは
現状の評価ではないと感じます。
国税庁が公表している
開業税理士は
全国での税理士登録者数81,000人
のうち55,000人になり
約68%が開業しているため
ほとんどが独立している
とは言えないと考えられます。
こういった細かなところは
業種を深く確認してみないと
実態の状況を確認できないので
すべてjob tagに頼り切りになる
のは危険かもしれません。
編集後記
job tagはあくまでも
あなたの職業選択のなかで
適性の可能性がある表示です。
仕事の本質は働いてみない
実態はわかりませんし
職業への感じ方は人によって
千差万別です。
ただ、長く働くことで知識や
経験、仕事をする方法を学ぶ
ことができて
あなたが仕事に合わせることが
できるようになる可能性はあります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務